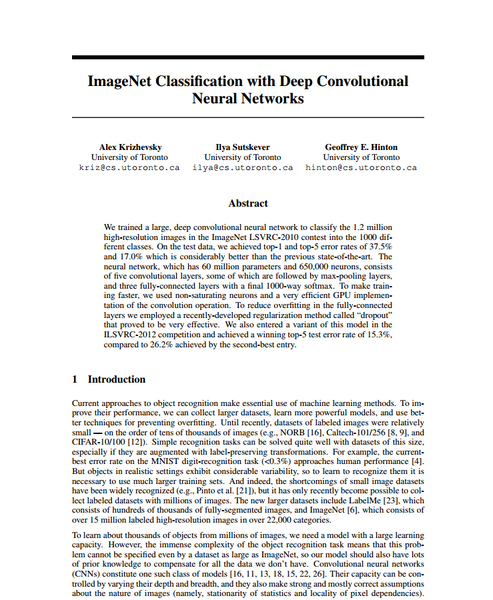国内の”知の最前線”から、変革の先の起こり得る未来を伝えるアスキーエキスパート。KDDI研究所の帆足啓一郎氏による人工知能についての最新動向をお届けします。
人工知能の技術の発展に関する華やかな話題が連日メディアを賑わしている。また、実際に「人工知能」の活用をうたうサービスを提供する大小さまざまな企業が登場している。この流れを受け、自社のビジネスにも人工知能が活用できるのではないか?と、考えている読者も多いだろう。確かに、人工知能はうまく利用すればあらゆる事業の助けになりえる技術である。しかし、有効活用するためには気をつけなければならないポイントも多い。そこで今回は、技術としての人工知能をきちんと活用するために、ユーザである人間にとって必要な心がけについて紹介したい。
深層学習というブレークスルー
人工知能に興味を持っている読者であれば、どこかで以下の動画を見たことがあるかもしれない。
Preferred Networks社がYouTubeにアップしている動画「分散深層強化学習によるロボット制御」
この動画では、強化学習と深層学習(Deep Learning)を組み合わせたアルゴリズムに基づき、ロボットカーが知識ゼロの状態から、スムーズな運転の動作を自動的に学習していく様子が紹介されており、見た目にも学習の過程がわかりやすい。
AlphaGoがプロ棋士に勝利したことや、コンピューターが猫の画像を認識できるようになったニュースなどで、人工知能のブレークスルーとなったアルゴリズムとして、特に「深層学習」が大きく取り上げられている。ここから、人工知能あるいはその要素技術としての深層学習が、あらゆる課題を解決してくれるイメージを抱いている人が多い。そして、自社にとってのビジネス課題なども人工知能によって解決できるのでは?という期待感を持つ人、あるいはそういった期待感を抱かせるような売り文句で「人工知能」を活用したサービスを提供する人や会社が増えている。
しかし、実際に人工知能をビジネスの現場で活用する場合、すべてを任せられるわけではなく、むしろ、活用する側にもそれ相応の“覚悟と努力”が必要となる。まずは深層学習にスポットを当て、この難しさについて説明する。
深層学習は万能ではない
深層学習は、昨今の人工知能ブームのきっかけを作った大きな技術的ブレークスルーであることは間違いない。このことから、「世界最先端の」深層学習によってあらゆる課題が解決できるのでは?という期待感を持つ方は多いだろうが、実は深層学習を有効活用できるための条件はかなり限定されており、実用できる場面は意外と少ない。
学術的に深層学習が広く知れ渡るようになったきっかけのひとつは、機械学習に関する代表的な国際会議「NIPS 2012」にて、トロント大(当時)の Geoffrey Hinton(ジェフリー・ヒントン)教授らによって発表された以下の論文である。
A. Krizhevsky, I. Sutskever, G. E. Hinton: ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks, Proceedings of NIPS 2012, pp. 1097-1105, 2012.
この論文では、任意の画像に写っている物体を認識する「一般物体認識」という研究課題において、深層学習を適用することにより、それまでの既存研究での認識精度を圧倒的に上回る成果が報告された。
また、Googleらによって発表された以下の研究は、「Googleの人工知能が『猫』の概念を発見した」という文脈で、当時Web上でも大きな反響を呼んだ。
Googleの深層学習によって「発見」された「人の顔」「猫」「人の身体」の画像(実際には深層学習の中での特徴的なニューロンを可視化した合成画像。下記論文から引用) Q. V. Le, M. Ranzato, R.Monga, M. Devin, K. Chen, G. S. Corrado, J. Dean, A. Y. Ng, “Building High-level Features Using Large Scale Unsupervised Learning”, Proceedings of ICML 2012, 2012.
この結果が達成できた要因は、深層学習自体にもあるが、学習のために膨大な量の画像データが使われたことも大きい。前者の研究では、ImageNetという、一般物体認識の精度を評価するための標準的なデータコレクションに含まれる120万枚の画像とカテゴリ情報(各画像に何が写っているのかを示す正解ラベル)、後者の研究では、1000万件のYouTube動画から抽出されたサムネール画像がそれぞれ活用されている。
さらに、画像というメディア自体が有する特徴にも、深層学習が有効に機能する要因がある。深層学習が登場する以前の一般物体認識の研究では、画像から抽出しうる多種多様な特徴、たとえば、色やテクスチャー、カドやフチといったエッジ(撮影対象物の形状)などから、物体認識に効果的と思われる特徴量を研究者が取捨選択・加工して、機械学習のアルゴリズムに入力させる方式がとられていた。
逆にいうと、”多種多様な特徴の中から適切なものを選別すること”がこの研究の難しさであり、世界中の研究者が腕を競っていた領域でもあった。この領域に対し、それまでに扱うことが不可能だった膨大な量の画像から、抽出しうる全特徴を抽出し、一般物体認識に有用な特徴を自動的に選別する技術として登場したのが深層学習である。
以上からわかる通り、深層学習が真に威力を発揮するためには、以下の条件が揃っているのが望ましい。
- 分析(学習)の対象となるデータが膨大にある
- 上記データの特徴が不明確かつ大量にある
- 豊富な計算機資源がある
さて、この条件を満たすだけのデータを分析しなければならないビジネスの場面はあるだろうか?
たとえば、大量のテキスト文章を分析したいというニーズはビジネスの場面ではよくあるが、そもそも分析したいテキスト文の量はどのくらいだろうか。数万件~数十万件程度の規模では、上記の各研究ほどのインパクトを出すためにはデータ量が圧倒的に少ない。むしろ、この程度の規模であれば、既存の機械学習技術(たとえばサポートベクターマシン、ベイジアンネットワーク、決定木など)でも十分に良い結果が得られることが多い。さらに、テキストの場合は画像と異なり、分析するための特徴としては「単語」という明確なものが定義されているため、上記の(2.)の条件にも適合していないことがわかる。
深層学習に限れば、想定されている利用場面のほとんどにおいて見合わない技術といえる。データ分析の経験が豊富な技術者であれば、こうした特長をきちんと理解したうえで、無理に深層学習を勧めず既存の技術の活用を促すだろう。しかしそのことにより、あくまで「深層学習」というバズワードに乗っかって仕事を進めたい現場やビジネスサイドの思いとすれ違う場面ができているのであれば、それは憂慮すべき事態である。
人工知能という技術の扱い方
では、利用場面に応じた適切な選択をすれば、人工知能によって課題が自動的に解決され、我々人間は楽をすることができるのだろうか。答えは部分的にはYESだが、むしろ人工知能の活用によってさらに素早い判断が必要だったり、データ分析・理解の能力がこれまで以上に求められたりするというのが実態である。
冒頭に紹介した自動運転の動画では、ロボットが運転している様子を放置しているだけで、自動的に運転技術を獲得しているように見える。しかし、こうした結果が得られている大きな理由は、人間がロボットカーに対し、明確な目的をきちんと与えているからである。具体的には、「速く移動する」ことに報酬を与え、「他のロボットカーや障害物への衝突および減速」に対しペナルティを課すという、シンプルかつ明確な枠組みが設計されている。シンプルな枠組みの中で学習を重ねることにより、効率的に自動運転技術を獲得できるのである。
一方、ビジネスの現場において求められる目標は、一見シンプルなものも多いが、実は複雑な要素がからみあっていることが多いだろう。たとえば、「売上を増加させる」、「製造ラインの歩留まりを下げる」といった目的は、最終的には数値として定義できる目標だが、その数値に影響を与える要素が多岐にわたっているため、現状の人工知能が扱えるほどシンプルなものではない。したがって、人工知能を有効活用するためには、人工知能(の要素技術)の特性をきちんと理解したうえで、技術で解決できる程度の細かい課題を洗い出し、適材適所で人工知能を当てていくという戦略が不可欠である。
さらに、いったん作った人工知能のモデルであっても、入力される情報は日々刻々と変化していくため、その有効期間は限られており、実際には人工知能を活用するシステムをただ作っただけでは世の中の動向変化に追従できないことが多い。したがって、人工知能を運用する人間にて、外部の動向に合わせたチューニングを常に実行できる体制と計算機リソースが必要である。
現状、実用レベルに達している人工知能を、あえて人間にたとえてみると、下記のようになる。
●自分の能力でできる範囲内の仕事であればものすごい早さで完遂できる
●自分の能力を超える仕事は一切やらない/できない
●外部状況の変化への対応は苦手で、その都度詳細な指示が必要
……という極端な人材と考えてよい。自身の部下や同僚として考えた場合、正直、扱いが難しい部類に入るのではないだろうか。
だがこのような極端な人工知能でも、すでに技術として活用している企業は当然ある。たとえば、日立製作所では、自社で開発している人工知能技術を活用し、工場での生産性を高めたり、実店舗での店員配置を変更することによって顧客単価を改善したりするソリューションを実用化している。また、筆者が所属するKDDI研究所においても、まだ実証段階ではあるものの、人工知能を活用したネットワーク自動運用システムを開発しており、将来に向けて複雑化が予想されるネットワークの運用現場の効率を上げようとしている。
今後、技術の発展によって、いろいろな場面で応用が効く人工知能の実現が待たれるが、少なくとも直近では人工知能の能力は限られており、そのことを人間が認識する必要がある。ただし、特に仕事のスピードを上げるためには、もはや人工知能の活用は不可避であり、この流れに乗らないわけにはいかないのも事実である。人工知能が人間に対して圧倒的に優位な仕事のスピード、そして無限のスタミナを賢く活用することにより、自身の仕事の付加価値を高めることができれば、当面は人工知能が生み出す新しい、そしてより人間の叡智が求められる高度な仕事に注力することができるだろう。
アスキーエキスパート筆者紹介─帆足啓一郎(ほあしけいいちろう)
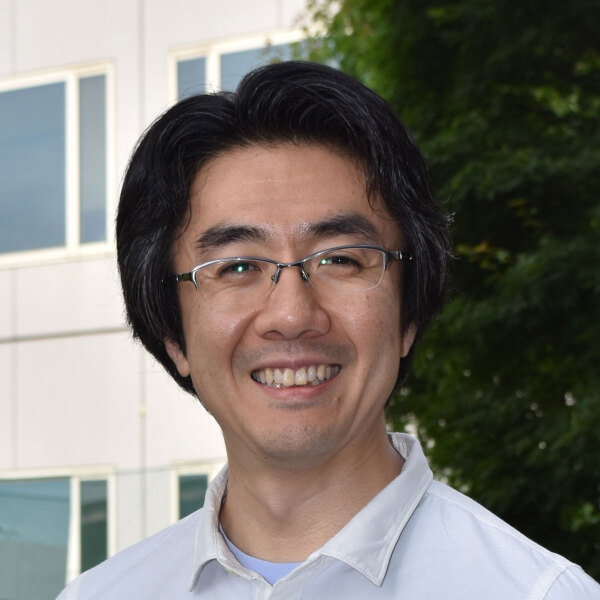
1997年早稲田大学大学院修了。同年国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社。以来、音楽・画像・動画などマルチメディアコンテンツ検索の研究に従事。2011年、KDDI研究所のシリコンバレー拠点を立ち上げるため渡米し、現地スタートアップとの協業を推進。現在は株式会社KDDI研究所・知能メディアグループ・グループリーダーとして、自然言語解析技術を中心とした研究開発を進めるとともに、研究シーズを活用した新規事業創出に取り組んでいる。電子情報通信学会、情報処理学会、ACM各会員。経済産業省「始動Next Innovator 2015」選抜メンバー。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう