Twitterは”ぼっち”たちの道具だった:仮想報道
2015年07月07日 07時30分更新
 |
|---|
電子版週刊アスキーにて好評連載中の「仮想報道」よりバックナンバーをピックアップしてお届けします。Twitterの企業買収にまつわるエピソードから見えてくるFacebookとの違いとは。前回「TwitterとFacebookの企業文化の違いとは:仮想報道」の続きです。※一部内容は連載当時のままです。
Vol.836 ツイッターの2人の創業者は意外に仲良し?
(週刊アスキー2014/8/12号 No.990より)
テレビドラマになるツイッター創業物語
ニューヨークタイムズの記者ニック・ビルトンが書いた『ツイッター創業物語』は、ツイッターは4人の創業者が貢献してできあがったものという立場をとっている。
そのひとりでツイッターのアイデアを考えたプログラマーのジャック・ドーシーは、CEOになったものの、経営能力がないと見限られて発言権のない会長の地位に追いやられた。しかし憤懣やるかたない彼は、画策し、替わってCEOになったエヴァン・ウィリアムズを追い出した。復権したドーシーは、別会社のCEOを務めていることもあってツイッターのCEOにはなっていないが、ふたたび大きな発言力を持つようになっているようだ。ビルトンの本はその最高幹部のドーシーに対してきわめて厳しかった。
アメリカではこの本をもとにしたテレビドラマまで作られるそうだ。たしかに、多くの人びとが日常的に使っているソーシャルメディアの会社のなかで、4人の創業者のあいだに亀裂が走り、投資家をまきこんで陰謀が繰り返されてきたというのは、それだけで興味を持たれるだろうし、友情と裏切りの物語はテレビドラマの素材としても打ってつけだ。
登場人物の逸話にもこと欠かない。
ツイッター設立時に資金を出したエヴァン・ウィリアムズは、ブログ・ツール「ブロガー」の生みの親だ。グーグルに売却して若くして大金持ちになり、ネット界で知られた存在だ。また、ジャック・ドーシーは「イケメン」で、メディアの寵児となってセレブ入りしている。おまけに、スティーブ・ジョブズをはじめ大勢の経営者のCEO教育を請け負ってきたビル・キャンベルという人物は、バックアップしていたはずのウィリアムズを追い落としてしまう。
フェイスブックの誕生を描いた映画『ソーシャル・ネットワーク』は日本でも当たったが、ビルトンの本を原作にしたドラマはツイッター版『ソーシャル・ネットワーク』になることだろう。
ツイッターは「ぼっち」たちの道具?
しかしながら、ドーシーはこのようにさんざんに言われたままなのだろうか。反論していないのかとインタビューを探しまわったが、見つからなかった。替わりにドーシーに取材して書かれたと思われる「ニューヨーカー」誌の長文の記事が見つかった。2013年10月21日の記事だが、ビルトンの本の引用もされており、本の内容を知ったうえで記事は書かれている。
この記事でドーシーは、ビルトンの本ほどはひどい人物になっていない。ビルトンの本でもドーシーがツイッターの誕生時に重要な役割を果たしたことは否定していないが、この記事でもそうだ。
ドーシーは「オデオ」という会社に勤めていたときにツイッターのアイデアを提案した。ニューヨーカーの記事によれば、エヴァン・ウィリアムズとともにオデオを設立したノア・グラスがドーシーのアイデアを支持し、その開発を進めさせた。
前々回書いたとおりドーシーは、ツイッターを自分の状況を語る個人的な道具と見ていたし、ウィリアムズは、いま何が起こっているかを知らせるニュース的なメディアと見ていた。それに対しノア・グラスは、パートナーと別れて孤独を感じていたので、孤独を感じている人びとが互いに語り合うことでその思いを減らすことのできるところにツイッターの価値を見出した。
いま日本で使われている用語で言えば、ツイッターは、「リア充」ではなく「ぼっち」たちの道具というわけだ。ビルトンは、創業者たちがこのようにそれぞれの思いを持ち寄ってツイッターを育てていったと見ている。
しかし、ニューヨーカーのD・T・マックスの記事は、ツイッターの会話的な機能はグラスではなく、利用者の発案によるものだと言っている。たしかに@をつけて特定の人に向けて書くなどというやり方は、利用者が勝手に始め、会社はそれを追認したにすぎない。
このようにD・T・マックスの記事は、ほかの創業者たちの貢献度を減らす形で、ドーシーの重要性を確認している。
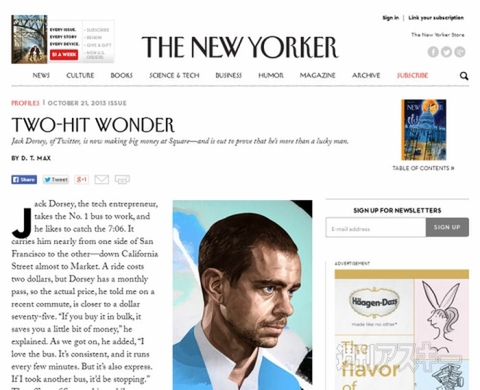 |
|---|
| 2013年10月のツイッター創業者ジャック・ドーシーについてのニューヨーカーの記事「二発屋(TWO-HIT WONDER)」。モバイルでの決済ビジネスは競争が激しい領域だが、ドーシーは簡便な決済のツールを開発して自分がたんなる「一発屋」ではないことを証明しようとしているというのが、この記事タイトルの主旨だ。 |
| 記事へのアクセスはこちら。 |
さっさと趣味のヨガ教室に行ってしまうCEO
けれどもこの記事も、ドーシーが経営者としてうまくやれなかったことは認めている。ドーシー自身も「もっとうまくやる方法はいくらもあった」と失敗したと思っているという。ただしドーシーは、しょっちゅうシステム・ダウンを起こすツイッターの問題にうまく対処できなかったのは、オデオとは別に新たな会社を作ったため人員も設備も十分ではなかったからだと弁明しているという。
この記事もビルトンの本と同じく、社員たちがドーシーの振る舞いにいらだっていたことも指摘している。ドーシーはあれこれやりたいタイプの人間らしく、夕方になるとヨガ教室に行くために早々に帰ってしまった。彼のこのような態度に社員たちは不満を感じていたというのだ(もっとも、戻ってきて仕事をしたというのがドーシーの言い分だが)。
ウィリアムズの追放についても、ドーシーは、取締役会での投票権もない自分は積極的な役割を果たしていないという。ドーシーのこのような反論を紹介しているが、その一方ドーシーは、いろいろな人が会社のありようについて自分に不満を言ってきたのでウィリアムズの追放に手を貸したとも言っている。
何でもありのIT起業家の世界?
こんなことがあったのだからドーシーとウィリアムズはさぞ仲が悪いのだろうと思うが、この記事には不思議なことも書かれている。
ツイッターで飼い殺し状態になったドーシーは、自分が無能ではないことを証明したいこともあってスクエア(Square)を設立した。この会社は、クレジットカード決済ができない小さな商店や個人などの事業者もスマートフォンに接続することで簡単に決済できる装置を作っている。おもしろい事業ではあるが、なんとウィリアムズが投資家を紹介しているのだという。ウィリアムズ自身もスクエアに投資したいと言っているのだそうだ。
この事業の将来性を感じてのことだとしても、自分を苦境に追いやった人間とまた手を組もうというのは、ウィリアムズはそうとうのお人好しなのか。あるいは個人的な感情はともかく儲かるならば、ということなのか。
ウィリアムズは、「ここ数年、ジャックの観察者として彼のことを見てきて、仕事や自分自身に対する集中の度合いがどんどんいいものになってきている」とドーシーを評価しているという。
もともとツイッター社の設立時にウィリアムズは、投資家たちの危惧にもかかわらず、ドーシーをCEOとして育てていきたいと思い、その地位に就けた。その後、裏切られはしたものの、こうした発言を知ると、ビルトンの本は大げさに書かれていて、ツイッターの創業者のあいだで深刻な諍いがほんとうにあったのかという気もしてくる。
自分のことがわかっていない目立ちたがりが最大の問題点?
マックスの記事は、ドーシーが希望している将来の仕事の話で終わっている。
彼はニューヨーク市長になりたいのだそうだ。大統領選挙のおりにオバマの市民集会で司会をしたときには、かちんこちんになって、汗びっしょりだとロサンゼルスタイムズに書かれた。それぐらい人と接触するのも苦手なのに、とマックスは書いている。ビルトンも、ドーシーは自分の役割を過大に語り、自分だけでツイッターを作ったような話をメディアに流していると批判していた。
自分のことがいまひとつよくわかっていなくて目立ちたがるというのが、このツイッター創業者の最大の問題点なのかもしれない。
Afterword
『ツイッター創業物語』では、ドーシーがツイッターをフェイスブックに売ろうとしていたと書かれていたが、上記のニューヨーカーの記事も、ドーシーは、フェイスブックのCEOザッカーバーグとしばしば食事をしていると書いている。ただし、アイデアをとられないように、警戒しながら会話しているのだそうだ。
7月7日(火)発売の週刊アスキー最新号では、「コンピューターによる脳の再現が可能な理由」についてレポートしています。電子版の購入方法はこちらから。
画像:Howard Lake
●関連サイト
歌田明弘の『地球村の事件簿』
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります





