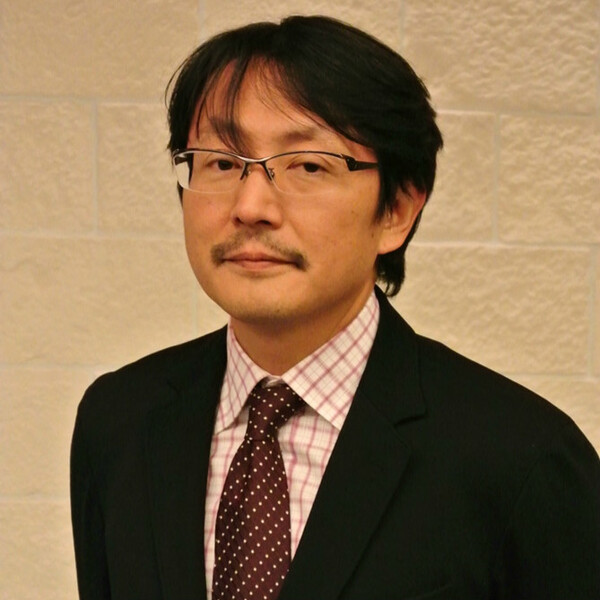自動運転は通信インフラと法整備がネック
夢の「完全なる自動運転」に向けて、世界各国の自動車メーカーやサプライヤー、研究機関が開発を進めている。しかし、いまのところ、自動運転システムと呼べるレベル3は実用化されていない。
レベル3とは「運転自動化システムがすべての運転タスクを実行する。実行中であれば、ドライバーは何もしなくてよい。ただし、作動継続が難しくなったときは、ドライバーが交代する」というもの。システムが順調に働いているときは、ドライバーは、運転どころか監視さえしなくていいのだ。逆に言えば、このレベル以上を実現してこそ、自動運転システムと呼べる。
開発の最前線では、これを上回るレベル4の車両もできあがっており、数年前から公道における試験も実施されている。しかしそれでも世の中では、その下のレベル3が実用化できていない。
開発が進んでいるのに、レベル3が実用化できない。それには大きく2つの理由がある。
ひとつは、技術的な難しさ。ドライバーの監視なく、安全なる走行を確実に行なうには、技術のさらなる熟成が必要だ。「10中8、9は成功する」では困る。「ほぼ失敗はありません」というところまでいかないと危険だ。そのためには、センシングからAIにおける判断、車両の制御、マップの作り込みや標準化などの幅広い技術が、今よりもさらに向上する必要がある。
また、レベル3の難しさには「作動継続が難しくなったときは、ドライバーが交代する」という部分にもある。たとえば交通事故が発生して、信号ではなく警察官が手信号で交通整理をしていたとしよう。そんなとき、当然運転自動化システムはギブアップして、ドライバーに運転を交代してもらうことになる。
ところが、そのときにドライバーが熟睡していたらどうなるのか? もしも、ドライバーがなかなか起きなかったらどうするのか。また、突発的な状況変化で、いきなり運転自動化システムが作業継続になったときはどうするのか。どれくらいの移行時間を用意すれば安全に運転を交代できるのだろうかという問題もある。
レベル3ではクルマの外だけでなく、車内のドライバーも監視し、どのようにシステムと人がコミュニケーションを取ればいいのかという課題もある。まだまだ技術的なハードルが残っているのだ。
自動運転で事故を起こしたときの責任の所在は?
さらに困るのが2つ目の問題だ。それは法整備が追いついていないこと。レベル3以上になると、運転自動化システムだけで運転するという状況が生まれる。そこで交通事故が起きたら、いったい誰が責任を取るのか? ドライバーの責任になるのか? そこがまだ明確に決められていない。
しかし、レベル4以上になると運転スキルを備えていない乗員が乗っているケースもある。その場合、乗員に責任を求めるのは酷だ。では自動車メーカーが責任を取るのかというと、それは自動車を販売する側にとって非常に高いリスクとなる。そこを、どこに落とし込むのかが決まっていないのだ。
そもそも、世界各国が批准しているジュネーブ条約やウイーン条約では「クルマには運転者がいないといけない」と決められている。そのため、誰も監視者のいないクルマを走らせることはできないというのが、現状の大前提だ。
日本ではこの条約を守るために、レベル4の公道試験をするときは、必ず遠隔操作で人間が見守ることが求められる。しかも、万が一のときは、遠隔操作で事故を防ぐことが求められる。ところが現状の通信インフラだと、通信速度が遅いためタイムラグが生じる。あまりにも走行スピードが速いと操作が間に合わないため、実情として時速15㎞程度での試験走行しかできないという。
そうした法制度の改正に向けて、国連や世界各国で話し合いが進められているのが現状だ。技術が先か、法制度が先なのかはわからないが、レベル3以上の自動運転システムが実用化されるには、その両方の課題をクリアする必要がある。だが、世の中は5Gを含め大きく動いている。その課題の克服は数十年単位ではなく、数年単位と考えていいだろう。胸を張って、「自動運転システム」と呼ばれるクルマが登場するのは、もう間近に迫っているのだ。
筆者紹介:鈴木ケンイチ
1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレース(マツダ・ロードスター・パーティレース)に参戦。新車紹介から人物取材、メカニカルなレポートまで幅広く対応。見えにくい、エンジニアリングやコンセプト、魅力などを“分かりやすく”“深く”説明することをモットーにする。
最近は新技術や環境関係に注目。年間3~4回の海外モーターショー取材を実施。毎月1回のSA/PAの食べ歩き取材を10年ほど継続中。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員 自動車技術会会員 環境社会検定試験(ECO検定)。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります