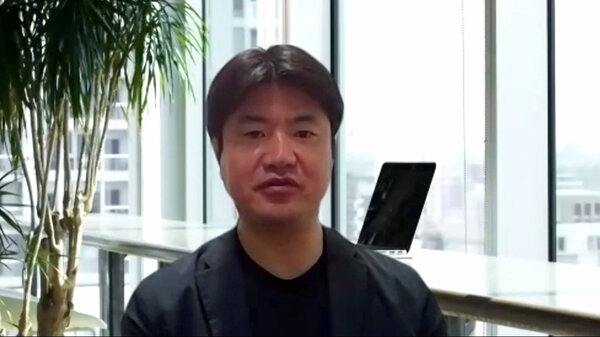「チキンラーメン」や「カップヌードル」などの即席麺を中心に幅広く食品事業を手がける日清食品グループは、DXに注力する企業として知られている。日清食品HDのCIO グループ情報責任者を務める成田敏博氏に、コロナ禍で一気に進んだペーパーレス化とシステムの内製化、そして新規事業とテクノロジーの関係について聞いた。
社内ではDXやデジタル活用の風が強く吹いていた
日清食品グループでは、2019年に「デジタル元年」のスローガンを掲げ、トップ自らが「デジタルを活用して働き方を変革していかなければ、グローバルカンパニーとして生き残れない」という強い危機感を社内に共有した。これにより、社内では業務改善の機運が生まれ、各部門でデジタル活用が模索されるようになった。
今回取材した日清食品ホールディングスのCIOである成田敏博氏がWebサービス事業者のメルカリから転職してきたのもちょうどこの時期で、以降は前任である喜多羅滋夫氏とともにDXを推進してきた(関連記事:ネット企業からエンプラへ 成田敏博氏が日清食品グループで挑戦すること)。結果、経済産業省と東京証券取引所が選ぶ「DX銘柄2020」「DX注目企業2021」にも選ばれた。食品メーカーとしては2社のうち1社だ。
現場での変革やツールの変更をともなうDXは、多くの企業で現場の抵抗を伴うものだが、日清食品グループでは前述したトップの覚悟が現場にも伝わっていたという。成田氏は、「入社したときから、DXやデジタル活用の風が社内で強く吹いていることを感じていました。トップの強いコミットメントのおかげだと思うのですが、DXの推進にあたって社内で抵抗を受けたことはほとんどありません」と振り返る。
この日清食品グループのDXは「NBX(Nisshin Business Transformation)」と呼ばれており、単なるデジタル化にとどまらないビジネスモデル自体の変革を目指す。NBXは大きくデジタルツールの活用やペーパーレス、ハンコレス、スマートファクトリーなどの「効率化による労働生産性の向上」と、タレントマネジメント、360°顧客理解、データドリブンなソリューション提案、サプライチェーンの清流化などの「ビジネスモデルの変革」という2本柱から構成されている。時代にあわせて働き方とビジネスモデルをアップデートしていくためにデジタルを活用していくという方向性だ。
これまで日清食品グループでは、各部門や部署がそれぞれの現場の課題に対して、デジタルツールの活用を進めていたが、今年の4月に日清食品HDにDX推進部を設立。まだ小規模ながら、関係部署と連携して、グループ全体のDX化を推進している状態だ。
ペーパーレスの延長上で進んだ「システムの内製化」はなぜ浸透したのか?
成田氏が最初に手を付けたのは、ペーパーレス&ハンコレス化。「入社した当時、デジタル化が思いのほか進んでいると思った反面、紙とハンコが業務に深く根付いているとも感じました。紙を回さないと業務が進まないという場面が多く見受けられたので、これをいち早くデジタル化したいと考えました」と振り返る。
そんな矢先、新型コロナウイルス感染症が世界的に流行する。「テレワークを浸透させるためにも、紙とハンコをなくしたいという声が現場から起こってきた」(成田氏)とのことで、100以上あった申請書類のデジタル化を一気に進めたという。まず現場と連携し、デジタル化やツール化が可能な業務をリストアップ。紙で管理していた申請書やワークフローをサイボウズのkintoneや電子署名ツールのDocuSignへと移行させた。
全社ぐるみでのペーパーレス化・ハンコレス化の恩恵は大きい。「今まで紙やExcelで管理していた内容をkintoneに載せることで、リマインドが自動化され、関係部署の参照権限もコントロールでき、過去のデータも探しやすくなりました。事業会社の1つである日清食品では、電子化によって稟議書やその添付資料など4万枚の紙がゼロになりました。起案から承認まで平均20日かかっていた稟議を平均4.4日にまで短縮できました」と成田氏は語る。
そして、こうしたデジタル化の過程で進んだのがシステムの内製化だ。従来のようにシステム開発を外部のITベンダーに依頼しているとコストも時間もかかるし、なにより俊敏性が得られない。こうした課題を感じていたこともあり、日清食品グループではkintoneやマイクロソフトのPowerPlatformを用いることで、自ら手を動かす内製化に舵を切った。つまり、現場のユーザーがベンダーからノウハウを獲得し、システム開発に取り組むようになったわけだ。
内製化に最初に興味を持ったのは、財務・経理部門だ。「もともと紙によって業務が煩雑化していたので、デジタル化の恩恵が大きかった。ITベンダーやIT部門よりも自分たちが手を動かした方が早いことにいち早く気づいたので、習熟も早かったし、開発できるメンバーの数も他の部門に比べて多くなっています」と成田氏は語る。
同時期に内製化を進めたのは、研究開発部門だった。これまで複数の開発プロジェクトをすべてExcelで管理していたが、kintoneを使うことでプロジェクトの統合管理が可能になった。「理系のメンバーが多いこともあり、ツールの習熟が非常に早かった。最初にレクチャーして以降は、自分たちでどんどん調べ始め、独自の使い方を学んでいってくれました」と成田氏は指摘する。紙中心の業務プロセスやExcelでの煩雑なプロジェクト管理など、リプレースしたい業務や仕組みが具体的にあったほうが、内製化へと進むエネルギーは大きくなるようだ。
なぜシステムの内製化が進んだのか? 成田氏はノーコード・ローコード開発のツールがここ数年で以前よりも使いやすくなった点を指摘する。「これは決定的なポイントです。以前はここまでのユーザビリティはなかった。今は、触ろうという意思がある人がツールを自ら学ぶことでスキルを得て、ノウハウをシェアするように変わってきた」と成田氏は語る。
もちろん、現場に対して内製化を強いたわけではない。もともとIT部門が開発を手がけていたが、現場部門とkintoneの画面を共有しながら対面開発をしていると、「これって自分たちでできませんか?」「自分たちでやってみたいです」という意思を示してくれる部署が少しずつ現れた。そのため、そういった部署にはIT部門が軌道に乗るところまでサポートし、あとは現場に任せているという。
内製化の浸透スピードは部署ごとに異なるが、現場に意思がある部署は、おおむね内製化の浸透も早いようだ。内製化で生まれたアプリで時間やコストの効果が現れると、開発したメンバーが評価され、モチベーションが上がり、さらにスキルを高めて別の業務改善を進めるという、プラスのループに入っていくという。「十分な意思を持たない部署には浸透させるのが難しいので、IT部門は引き続き開発を担当します。ただ、他部門がうまく行っているのをみると、自然と意識が高まるようです」と成田氏は語る。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります