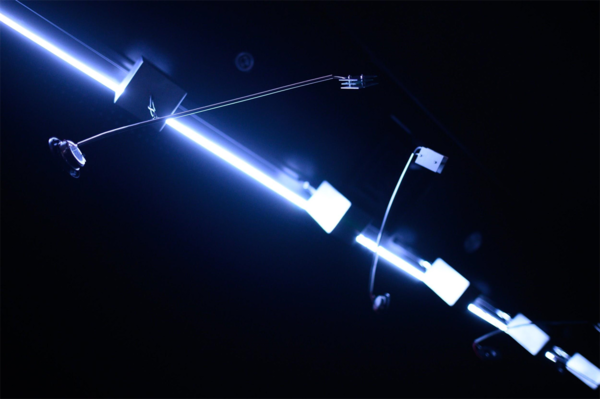AIの次は「ALife」!?
AI(人工知能)という言葉はよく耳にするようになったが、ではALife(人工生命)はいかがだろう? 耳慣れない単語だが、じつはAIに負けず劣らずエキサイティングでいま熱い分野なのだ。
ALifeは人工生命と訳されるが、「我々の知っている生命」を対象とする生物学とは異なり、「ありえたかもしれない生命」すべてを対象とする。つまり、AI以上に幅広い研究分野だ。最近では、未来の生活や街作りを考える上で欠かせない視点であるとして、ALifeには熱い視線が注がれている。
そこで今回は、日本のALife界を牽引している東京大学の池上高志教授と共同でALIFE Lab.の代表を務める青木竜太氏、オルタナティヴ・マシン代表の升森敦士氏、そして電通国際情報サービス(ISID)のオープンイノベーションラボ(イノラボ)でプロジェクトマネージャーを務める藤木隆司氏のお三方に、ALifeの概要から今後の展開まで広く話をお聞きした。
―― まず、お三方の略歴と、現在の活動内容を教えてください。
青木 僕はコンセプトデザイナー/社会彫刻家という肩書でありうる社会を試作・思索する活動をしています。
ALifeの活動をすることになったのは、欧州と米国の学会を統合し、初めての人工生命国際学会「ALIFE 2018」を日本で開催するということになり、その開催の2年前、2016年に企画・運営に声をかけてもらったのがきっかけです。カンファレンスをやって終わりだともったいないので、社会的つながりをもったコミュニティを構築できるようにALIFE Lab.という構想を提案し池上らと一緒に活動を開始しました。
そして2017年にはALIFEの技術開発を専門でおこなうオルタナティヴ・マシン社を共同創業しました。最初は誰しもがビジネスにならないと言っていたのですが(笑)、ISIDさんをはじめ長期研究プロジェクトが増えるようになり、ありがたいことに徐々に仕事になるようになってきました。
2020年からは創業当時から一緒にプロジェクトをやってきた升森に会社を任せ、私はより社会応用やコミュニティー形成に注力するように体制を変えました。
―― それまではどのようなお仕事をされていたのですか?
青木 20代の頃はエンジニアをやっていまして、最初はWebサービスを提供する会社を立ち上げました。そしてもう少しコア技術に触れたいと思っていたところ、ちょうどデジタルテレビを動かすためのソフトウェアにニーズが集まり始めまして、組み込み系OSやグラフィックエンジンの分野にも手を伸ばしました。そして2006年からはPS3のCELLプロセッサで動くソフトウェア開発を主に手掛けました。
―― ゲーム開発もされていた?
青木 じつはゲームではなく産業用です。どういうことかと言えば、当時、外観検査装置や監視カメラ、あるいはレーザー顕微鏡などのソフトウェア解析をする際に、「CPUのみでは非力だが、GPGPUはまだ一般的じゃない」という課題がありました。そこで、比較的安定しているPS3に計算をオフロードし、並列化させて計算しようと。他のチームは「気象シミュレーションをPS3で1000倍速くする」「PS3を1700台並列化させる」というようなことをやっていたり、そんな技術者集団に属していました。
升森 僕はALifeの研究者で、現在はオルタナティヴ・マシンと東京大学の特任研究員を兼任しています。学部生の頃はデジタルファブリケーション(Fab)の第一人者・田中浩也先生の研究室に、そして修士からは池上高志先生の研究室に所属して人工生命の研究を本格的に始めて、今も継続しています。
―― もともとはFabを研究されていたのですね。
デジタルファブリケーションは段階を進めていくと、いわゆるデジタルデータでデジタル工作機械を使ってものづくりをする、という単純なものではなく、物自体が小さなモジュールで構成されるといったようにデジタライズされていきます。
そうしたデジタライズされた物が「自然に、自律的に組み上がって形ができていく仕組み」が僕の学部での研究テーマでした。Fabという文脈でしたが、このころからすでに人工生命的なアプローチで研究をしていました。
藤木 学生時代から画像系のAIを研究していまして、就職でも画像系のエンジニアとして富士ゼロックスという会社に入社しました。その後、ディープラーニングが登場し、応用可能性が広がったタイミングで『新しいことにチャレンジしてみたい』と思い、オープンイノベーションスタイルで先端テクノロジーを使った新しいソリューションを社会実装していくイノラボの活動に惹かれてジョインしたのが2017年です。
―― もともとエンジニアだったのですね。イノラボには両方いらっしゃいますよね。社会学的な方とエンジニアリングな方と。
藤木 イノラボは新しい分野にを開拓してくために、テクノロジーの専門家のみならずUIUXの専門家やプランナーも在籍しているんです。
ALifeの父はフォン・ノイマン!
―― ALife、人工生命とはいつ頃生まれた概念で、どのように発展してきたのでしょうか?
青木 人工生命は「生命とは何か?」を探求する分野です。進化や意識など、あらゆる生命現象をソフトウェア、ハードウェア、ウェットウェア(化学反応)を利用して作りながら探求しています。
もともとはゲーム理論や原爆、コンピューターを生み出した天才数学者フォン・ノイマンが、1950年代に生物の振る舞いも計算機の振る舞いも同様に計算可能なことを示すモデルを作ったところから始まっており、ノイマンは人工生命の父と言われています。
人工知能の第一人者マービン・ミンスキーもフォン・ノイマンのお弟子さんの一人でして、ミンスキーは人工知能を、ノイマンは人工生命にそれぞれ興味を持ち、分岐していったという流れがあります。
その後、複雑系の研究などで発展していきながら、1987年にクリストファー・ラングトンというコンピューターサイエンティストが、それまでバラバラに研究していた「生命とは何か?」を研究している人たちを集めて学会を立ち上げたんです。それがALife、人工生命という分野が立ち上がった瞬間ですね。そこから今に至ります。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります