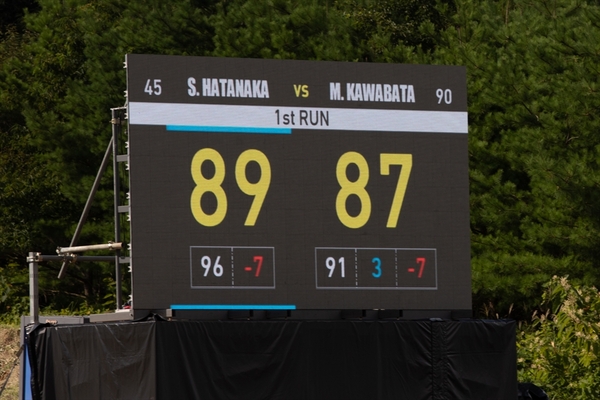採点方法がドライバーのレベルを押し上げる
誰よりも早くゴールするという一般的なモータースポーツと異なり、D1グランプリはフィギュアスケートや新体操と同じ採点競技だ。人が採点すると、そこにブレが出てくる。そこで公平さを得るため2013年シーズンから導入されたのが、D1独自の機械採点システム“D1オリジナルスコアリングシステム(通称:DOSS=ドス)”だ。DOSSでは、走行マシンの車速や角度、そして角度の安定性や振り返しの鋭さなどを数値化して得点表示するというもの。DOSSの導入により、わずかな車速変化や角度の乱れが得点に影響されるようになり、ドライバーには、これまで以上に繊細かつスムーズな技量が要求されるようになった。その一方で、オールドファンの中にはDOSSに対して批判的な意見があるのも事実だ。
「機械を使って採点するようになると、はっきりとわかるようになってしまうから、それが面白くないと(笑)。今までは曖昧だからそれはオカシイと言っていたのに、曖昧さを排除したら、今度はツマラナイになる。その塩梅がすごく難しい。では、走りのレベルが退化してしまったのかというと、そんなことはありませんよね。ここ数年のクルマのレベル、ドライバーの技術レベルはとんでもなく高いですよ。それに昔の方が面白いということで、当時のやり方に戻したら、世界から遅れをとってしまいます。“ドリフトは日本のお家芸。世界に勝たなければいけない”というわけではありませんが、D1グランプリは長年“速いスピードと凄い角度”を求めてやってきました。世界と比較した時、今のレベルはトップではないかもしれない。ですが年々技術レベルは進化しています。退化したと感じたことは一度もありません」

現在のD1グランプリでは「走行中に必ず通過しなければならないエリア」が設けられている(通過できなければ減点)。見る方としてはわかりやすく、ドライバーとしては厳しいエリアを通らないといけないため、技術の向上が図れる
エンターテイメント性も持たせつつ、競技としなければならない難しさがD1グランプリにはある。興行としての見せ方を工夫しながら、しかし着実にドライバーとマシンは進化し続けてきた。もし単なるエンターテイメント性だけに固執していたら、早晩飽きられて、今はなかったかもしれない。スポーツ性があるから続いたのだ。
D1グランプリがもっと発展するためにできること
20年間、試行錯誤と努力で競技へと発展してきたD1グランプリ。現在抱えている課題は二つだと鈴木さんは考えている。
「レギュレーションと見せ方でしょうね。見せ方では、現在YouTubeによるライブ配信を行なっています。サーキットに行かなくても、シリーズ戦を観ることができます。そのほか、公式チャンネルなどで様々な動画配信、そしてDVDを販売したり、媒体での情報発信をしています。もちろんSNSからも積極的に情報を伝えています。これだけで足りているとは思いませんが、時代に合わせて変化していく必要はありますね」

昨年行なわれたFIAインターコンチネンタル・ドリフティングカップの表彰式の様子。優勝は中央のロシア代表ゲオルギィ・チフチャン(愛称:ゴーチャ)選手で大会2連覇。2位はTeam TOYO TIRES DRIFT-1の藤野秀之選手。3位はイギリス代表のアンドリュー・グレイ選手
「繰り返しになりますが、レギュレーションはとても大事だと思っています。3年前からF1などの統括団体である世界自動車連盟(FIA)による国際格式の世界一決定戦「FIAインターコンチネンタル・ドリフティングカップ」が日本で開催されていますが、審査方法、車両規定、競技運営方法……、そこがわかりづらいのが現状ですね。過去3回の世界一決定戦のルールがすべて違いますからね。そういうのは世界戦としてありえません。モータースポーツ競技は100年の歴史があり、日本でも50年以上の歴史があります。でもドリフト競技は20年しかないのです。一方で先ほど申し上げた通り、厳格に決めていくと面白くなくなってしまう。その駆け引きが難しいですね」
そして鈴木さんは発展する上で、自動車メーカーの協力は不可欠であると考えている。D1グランプリの多くのチームはタイヤやチューニング系パーツメーカーなどのスポンサードはあるが、SUPER GTのように自動車メーカーそのものの参戦、いわゆるワークス体制のチームは存在しない。
「現在、アメリカとヨーロッパでは日本よりマルが1個違うところまでギャラが貰えるようになってきています。それは、海外の場合、自動車メーカーがエンターテイメントとして認めているからです。ですが日本のメーカーは、ドリフト競技に直接関与してきませんでした。ですが、ここ数年TOYOTA GAZOO Racingや日産自動車が、直接ではないにせよGRスープラやNISSAN GT-Rといった車両に関与するようになってきた。ですから、我々がちゃんとした一つのイベントとして、D1グランプリを作り上げれば、ステップが一段階上がるのかなと思っています。逆に言えば、今までできていないともいえます。ちゃんとした競技、ちゃんとした審査、ちゃんとしたイベントでなければ、世間は認めてくれないんですよ」
ドリフトは、峠や埠頭などで走り屋たちが行なっていたという悪いイメージがついている。以前、FIAインターコンチネンタル・ドリフティングカップ開催に際し土屋圭市さんにインタビューした時も、これからドリフトを盛り上げようとした時に、マスコミに叩かれ苦労したという話をしていた。それもあって、長年にわたり自動車メーカーから協力を得ることはできなかったのだろう。しかし、FIAによる世界戦も行なわれるようになるなど、ドリフトを取り巻く環境は大きく変わった。
前身であるビデオオプションの企画「いかす走り屋チーム天国」から30年。ドリフトはプロスポーツとなり、そしてFIAによる世界大会が開催されるまでに至った。それもすべてスポーツを意識してきたからだ。「D1グランプリは20年やってきてはいますが、勢いだけでここまできてしまっているので、いまだちゃんとできていないのかなと思います」。鈴木さんは自戒を込めつつもはにかんだ。
思い出に残るのは「初開催」
D1グランプリは世界中にドリフトの種を撒き続けた
20年間、のべ132戦のD1グランプリ・シリーズ戦の実況・解説をしてきた鈴木さん。その中で、思い出の残るのは「初開催の場所」だという。「ドリフトは小さいサーキットで開催することが多かったんですよ。今では聖地といっているエビスサーキットも小さなサーキットです。それもあって土屋圭市さんと、いつか富士とか鈴鹿といった国際サーキットでやりたいね、と話をしていました」
そして、2004年頃から、富士や鈴鹿、岡山国際、SUGO、筑波、オートポリスと日本の名だたるサーキットでシリーズ戦ができるようになった。
「大きなサーキットでやることで、D1はここまで来たんだと感動しましたし、それぞれの場所での思い出は残っていますね」と鈴木さん。そして初開催の場所といえば、東京のお台場だ。いわゆるサーキットのない東京都でモータースポーツ観戦ができたのはD1グランプリだけだ。それは広い敷地があれば競技ができる、というドリフトならではの特質だ。「お台場でやるようになった時もうれしかったですね。お台場の駐車場にスタジアムのようなスタンドを建設して。人が入るのかな? と心配したのですが、蓋を開けてみたら立ち見も含め1万人が訪れた時は感動しましたよ」。残念ながらお台場での開催は、東京オリンピックによる再開発により昨年で終了してしまった。東京オリンピック後に復活することを願わずにはいられない。
D1グランプリは海も渡った。「アメリカのアーヴィンデールという所に、何もわからずノリと勢いだけで行ったんですよ。実際金曜日は誰も来なかったですね。ですが日曜になると噂が噂を呼んで、物凄いお客様がいらっしゃったんです。現在アメリカでは、Formula Dがメジャー団体ですが、それよりも前にアメリカでドリフトをして、人々に認められた事が一番の感動といえるかもしれません。イギリスのシルバーストーンにも行きました。シルバーストーンといえば、モータースポーツの聖地ですからね。土屋さんと、とんでもない所に来てしまったって感動しましたよ。でも蓋を開けてみたら、お客さんがシーンとしていて(笑)。でもシルバーストーンで開催した後も、ヨーロッパでドリフトが定着していったんです」
アメリカ、そしてイギリスに持ち込まれたドリフト競技は、言葉など関係なく人心をつかむばかりか、世界各地でドリフト競技団体が立ち上がった。
「僕たちは、魅せ方や興行方法、技術などをただ置いてきただけです(笑)。言い換えるなら、やりっぱなし。あとは勝手に彼らが育てていったんですね。今ではヨーロッパやアメリカの方がD1より上かな? ホントに(笑)。あと、ロシアやニュージーランド、タイ、中国でも行ないました。僕たちは種をまいて、後は現地の人が勝手に水を撒いて育てて、気づけば自分達よりも大きくなっちゃいました(笑)。最初はどこでも同じで、皆さん半信半疑なんですよ。でも終わってみたら凄く盛り上がった」
ドリフトをする人はバカなんです
バカだから人の心をつかむんです
言葉を超え、そして初めて見る人の心をつかむドリフト。その要因はどこにあるのだろう?
「今までそういうモノがなかったからですよ。あと、これは世界のどこでもなのですが、ドリフトをやる人たちってバカなんです。バカって何かというと、物凄いことをして喜ばれることが好きな人種のこと。バカだからもっと喜んでほしいと頑張りすぎてクラッシュしたりするのですが、そこがウケたんです。クルマ同士がぶつかる、壁にあたる、白煙や音。この目の前で起きている非日常的なモノは何なんだろうというのがあるんですね」
さらにドリフト競技で日本車が使われていた、というのも一つの要因だと鈴木さんは語る。「ヨーロッパはBMW、アメリカならV8エンジンを使ったりというのはありますけれど、ドリフト車両のベースはいまだにシルビアなど日本車のチューニングカーが主流です。普通モータースポーツは常に最新のクルマを追いかけますけれど、ドリフトは中古車を買ってきて改造すれば誰もが楽しめる。コストが他のモータースポーツと比べて圧倒的に安いんですよ」
国内で人気のSUPER GTの場合、GT300クラスに参戦するには、車両価格だけで6000万円以上かかり、輸送費や人件費などを考えると最低年間予算は1億円以上と言われている。スーパー耐久の上位カテゴリであるGT4やTCRカテゴリでも車両価格で数千万はくだらない。だがドリフト車両のベースはシルビアの中古車。桁が大きく異なるのだ。参戦する側からすれば、比較的低予算でマシンやチーム運営ができる。
「併せて、日本車ブームというのもありますね。映画ワイルドスピードもいい例ですね。日本のチューニングカーが活躍する。それがいいのかもしれませんね」。世界各地でドリフト競技が行なわれるようになると、様々な専用パーツが出てくる。「面白いのは、みんな同じ方向でクルマをいじるんですよ。違う方向に行かないんです。今では日本よりチューニングレベルが進んでいるかもしれません。今のD1グランプリの車両の中には、海外製パーツが数多く使われていますよ」
週刊アスキーの最新情報を購読しよう