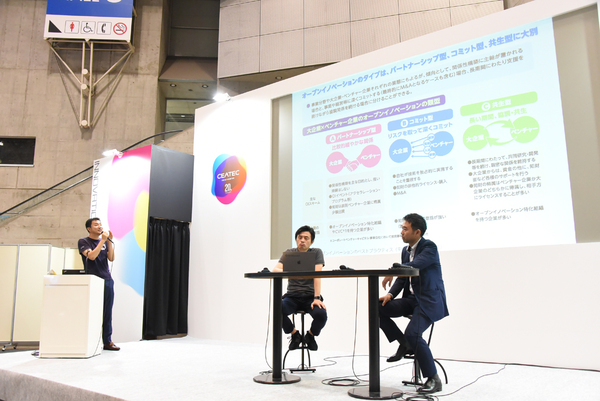CEATEC 2019セッション「STARTUPs×知財戦略~CVCを通じた知財の共創~」レポート
オープンイノベーションでベンチャーと組む知財意識
2019年12月04日 16時00分更新
特許庁は2019年10月15日、幕張メッセで開催された「CEATEC 2019」のイノベーショントークステージにてセッション「STARTUPs×知財戦略~オープンイノベーションを成功に導く知財の活用~」を実施。多くの大手企業がオープンイノベーションに取り組んでいるが、実際に事業化へとつながった例は少ない。大手企業とベンチャーとの協業を成功させるには、何が必要なのか。事業創造のプロとして大手とベンチャーの共創を支援しているコーポレートアクセラレーターが語る、オープンイノベーションを成功させるポイントとは。
世間はオープンイノベーションブームだが、成功例はあまり聞かない。プログラムをやってみたものの、事業化につなげるのは難しいと言われている。「STARTUPs×知財戦略~オープンイノベーションを成功に導く知財の活用~」では、コーポレートアクセラレーターを支援するゼロワンブースター 合田ジョージ共同代表/取締役と、リバネス 長谷川和宏執行役員CKOをパネリストに迎え、「協業に取り組む姿勢」、「知財の帰属や成果の活用制限」、「契約の詰めvs物事を進めるスピード」、「最近の取り組みについて」の4つのトピックについて議論した。モデレーターは、特許庁 企画調査課 スタートアップ支援チームの菊地陽一氏が務めた。
大手企業とベンチャー、協業に取り組む姿勢はどうあるべきなのか
菊地氏(以下、敬称略):大手企業とベンチャーは、それぞれどのような意識でオープンイノベーションに取り組むと成果が上がるのでしょうか。 これまでのご経験から、成功例、失敗例があればお話しいただけますか。
合田氏(以下、敬称略):トップダウンがうまくいきそうですが、実はうまくいきません。ボトムアップは今のところ成功例はゼロ。ミドルにやる気があり、トップを口説いて、ゴー、サインが出たときのみ、成果が出ると思います。組織的には、新規事業部が事業部と並列している構造の場合、反発されやすいですね。できれば、新規事業部は本社企画部にあったほうがベターです。
取り組む姿勢として、アクセラレーションプログラムは新規事業部をやるためではなく、環境を作ることです。大企業にとってベンチャーとの協業は、事業としてのインパクトはそれほど期待できません。取り組みによって会社の中にイノベーションを起こし、協創の場をつくること自体がプログラムの目的と考えたほうがいいでしょう。マインドセットとして、スタートアップとともにエコシステムを高め合っていこう、という気持ちをもっているかどうかが大事ですね。
菊地:アクセラレーションプログラムでは、「新規事業を創るためにがんばります」、と皆さんおっしゃっていますが、それが目的になってしまうといけないのですね。
長谷川氏(以下、敬称略):大企業にやめてほしいのは「情報交換をしたい」というスタンスから始めようとすること。何を一緒にしたいのかわからないと、ベンチャー側は何を話していいのかわからず、お互いに表面的な話をするだけで終わってしまう。「これを一緒にやりたい」という仮説から始めたほうが1回目のミーティングがうまくいきます。また、会社の方針だからやるのではなく、担当者自身にやる気があり、責任と意思をもって取り組めるかどうかが大事です。
知財の帰属や成果の活用制限
菊地:実際に共同研究・開発をする段階になると、知財の帰属の問題がでてきます。共有特許では使いにくい部分もあります。協業のフェーズによって知財の扱いは変わってくるのでしょうか。
長谷川:現場の研究者同士ではお互いの貢献度がわかっていますので、帰属の話し合いでもめることはないですね。ただし、大企業の知財部の人が出てくると、ややこしくなることがあります。大企業の知財部は会社の権利を守ることを優先させるので、ベンチャーに不利な要求をしがちです。
合田:知財部門とベンチャーの間に担当者が挟まれていて、知財部とダイレクトと話せないのはキツイですね。直接話すと、案外スムーズに交渉が進んだりします。ここ数年間でスタートアップのスペックが相当上がっていますから、スタートアップのほうが交渉力は強いかもしれません。
長谷川:ベンチャーと組むには、知財部の意識を変えないと難しい。知財部では、リスクをヘッジする方法ではなく、ベンチャーと一緒にリスクをどう許容するかを考えてほしいです。
合田:確かに、日本の知財に対する考え方が根本的に間違えっているように感じています。本当は、守るためではなく、使うための特許ですよね。
長谷川:その守りの姿勢がオープンイノベーションのうまくいかない原因だと思います。大企業は100億を1千億にする知財戦略を長年やってきているから、0から1億をつくるときの知財の扱い方を忘れてしまっているんじゃないかな。
菊地:大企業と協業すると、他社競合との協業を制限されるケースもあると聞きます。こうした制約についてはどのようにお考えですか。
合田:出資を受けている場合は、知財の一部を相手がもっているようなものなので、ある程度の制約がかかるのは仕方がないかもしれません。しかし、大企業にはスタートアップに知財権を全部渡すくらいの姿勢であってほしい。世界に勝たなくてはいけないのだから、競業との争いを気にするよりも、ベンチャーにどんどん知財を活用して市場を大きくしてもらうことを優先したほうがいい。
長谷川:R&D系のベンチャーではあまりもめることは少ないのですが、共同研究には関係のない部分で、報告義務を付けられていたりするので、契約書の項目を見落とさないようにチェックしたほうがいいでしょう。最近はベンチャー側も賢くなり、専門家や特許庁にも相談しやすくなったので、昔ほど騙されたという話は聞かなくなりましたね。
菊地:スタートアップの交渉力が増している、というお話もありましたが、一方で契約交渉に不利な条項を入れられて苦労しているケースもあります。創業間もないスタートアップには、交渉は難しいのではないでしょうか。
長谷川:R&D型のベンチャーにとって、特許を読めないのは、論文読めないのに等しい。研究者であれば、契約書も理解しようと思えばできるはず。その重要性をどこまで認識できるかが勝負でしょう。自分で全部やるのは難しくても、今は専門家に相談できる環境があるので大丈夫だと思います。
ここで、相談できる専門家の代表として、エアロネクスト 中畑 稔取締役CIPOが飛び入りで参加。
中畑氏(以下、敬称略):例えば、あるAI画像認識のコア技術の特許を持つベンチャーが、その応用技術の知財ポートフォリオを作っていたとします。そこに医療分野の大企業と協業することになった際、そのユースケースの部分だけを切り離せるかどうか。最初から事業と知財を一緒くたにやっていたら、コア技術も大企業に持っていかれる可能性もありますし、ほかのユースケースには使わないように制限がかかるかもしれません。最初は厳しい契約条件が提示されても、たいていは知財部の方と直接話すと解決するケースが多いので、ベンチャーはきちんと交渉することが大事です。
合田:スタートアップが大企業とは交渉すること自体ができないと思っていることがありますね。契約内容が受け入れられなければ交渉すればいいのに、妥協したり、決裂したりしてしまうのはもったいない。
中畑:大企業が相手だと、最初から諦めちゃうところはありますね。大きな会社に認められたことを発信して、次につなげたい、という気持ちで妥協してしまう部分もあるでしょう。でも、最低限守るところは守るのが大事。今は専門家に相談しやすくなっているので、スタートアップも交渉力を実装してほしいと思います。
長谷川:従来の下請け用の契約書のテンプレートをそのまま使われて、成果物はすべて大企業側に帰属、支払いは6ヵ月後、といった契約内容のケースもあります。大企業が契約書を変えられないのであれば、業務委託にするなど、ベンチャー側から別の契約交渉を提示しないと厳しいですね。
スピードを損なわずに契約を進めていくには
菊地:担当者間ではうまくいっているのに、知財部が出てくるとぶつかってしまう。ということは、大企業側の担当者が、いかにうまく知財部や法務部を巻き込み、社内を説得するかにかかっているともいえます。
長谷川:必要であれば、社内で反対している人にベンチャーが出向いて直接プレゼンをするくらいのことをしてもいいかもしれません。たいていは大企業側の担当者も困っているので、突破する方法を一緒に考えられるような協力関係を築いておくことが大事。相手企業の人を自分の味方にできると交渉を進めやすいです。
中畑:従来の下請け向けとは違う、ベンチャー向けの契約のスタンダードがあってもいいかもしれませんね。
合田:日本では大手企業にスタートアップが合わせる、というのがデフォルトですが、グローバルでは、リバースインテグレーション型でスタートアップに大企業が合わせていく形へと変わってきています。この先、ルールを変えなくてはいけないのは大企業側だということは、相当に意識してほしいです。
中畑:そもそも産業構造が変化しているので、過去のものが使えるとは限らない。大小を問わず、時代にアダプトできる企業だけが生き残れるのではないでしょうか。知財についても同じで、専門家からのアドバイスをどう受け取るか。弁理士に勧められたから特許を出願する、というのではいけない。そもそも弁理士とスタートアップは、利益が相反しています。特許をたくさん出せば特許事務所が儲かるので、極端な話、何を出せばいいのかわからないスタートアップに対して情報の非対称性を利用した商売とも言えます。しかし、そのことに専門家自身も気付いていない。業界に参入するプレーヤー全員が、今の産業構造に合ったマインドセットに変えていく必要があるでしょう。
菊地:契約内容も大事ですが、スピードを優先させて、細かいところは妥協して進めたほうがいい、という考え方もあります。実際の契約のときに、最低限、決めておかないといけないことはありますか?
合田:もめる可能性があることを全部書いておくのが契約書なので、思いつく限り、すべて書いておくのが正解です。リスクと時間を含め、何を譲って何を譲れないかをいかに交渉できるかにかかっています。
東南アジアのベンチャーの知財戦略を支援する「NEST iPLAB」
最後に、リバネスとゼロワンブースターの最近の取り組みについて紹介された。
リバネスと中畑氏が代表パートナーを務める特許業務法人iPLAB Startupsは、東南アジアのスタートアップの知財戦略を支援する合弁会社「NEST iPLAB(https://www.nestiplab.com/)」を10月7日に設立。東南アジアには、高い技術力をもつスタートアップが数多く存在するが、国際特許の取得の難しさなど知財の面で課題を抱えている。日本の特許庁は、世界有数の審査クオリティで信頼性が高く、審査も早い。そこでNEST iPLABでは、オンラインのIP相談、日本とグローバルの特許出願・権利化を行なうフレームワークを提供することで、東南アジアのスタートアップ企業のグローバル展開を支援する。
ゼロワンブースターは、12月4日に国内最⼤級の事業創造カンファレンス「0→1 Booster Conference 2020」とイントラプレナーコミュニティイベント「Innov8rs Tokyo」を同時開催する。詳しくはHP(http://conference2020.01booster.com/)にて。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります