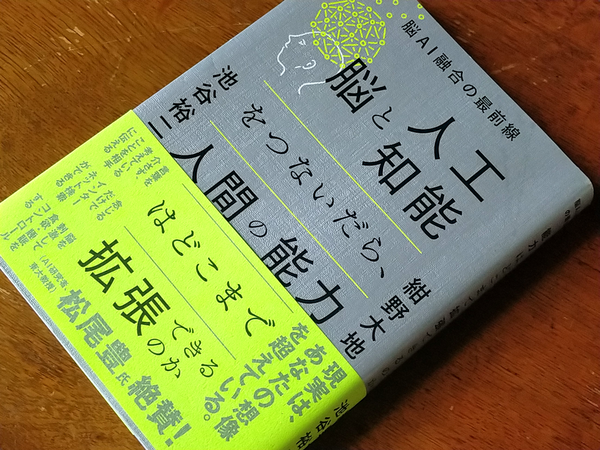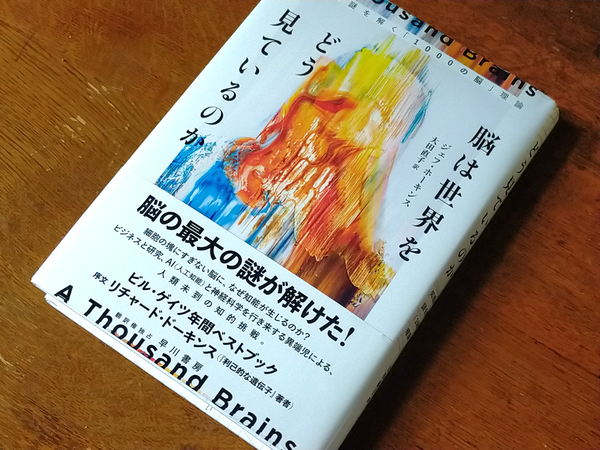未来のコンピューターは《脳型》か《脳とつながるコンピュータ》なのか?
いまのコンピューターはシステム全体が文字どおクロック(時計)仕掛けで、ビー玉1つ1つを順番に指で動かしているような仕組みだ。本当に子どものオモチャみたいな素朴なものである。それに対して、脳は、全体が理想的な都市のように生き生きと、しかも回路をたえず自ら書き換えながら動いている。つまり、それ自身が学習して進化している。
脳の《学習して自分を書き換えながら動いている》というしくみの凄さは、脳型コンピューターに取り組んでおられた松本元氏(当時電総研超分子部長・東大工学部教授・筑波大学情報工学系教授)に直接うかがった。『月刊アスキー』の1995年8~12月号で「脳型コンピューターを作る」という連載を掲載していたのだ。
1995年8月号 (第1回)脳ってどんなコンピュータ? p389~396
1995年9月号 (第2回)愛は脳を活性化する p317~324
1995年10月号 (第3回)神経細胞と人工神経素子モデル p389~396
1995年11月号 (第4回)時系列学習則と神経細胞の可塑性 p369~376
1995年12月号 (第5回)システムとしての脳の情報処理 p481~488
この連載のために、毎月、担当者にくっついてつくば市の工業技術院電子総合研究所にある研究室まででかけてレクチャーを受けるのが楽しかった。松本先生は、「脳を2cmくらいにスライスして砂糖水に漬けておくと2ヵ月くらい活動しているよ」などと言われたり、研究室の横に実験に使うイカの水槽があり、「イカは人の顔覚えるんだよねぇ」などど説明してくれる。
いまわれわれが寿司屋さんで新鮮なイカを食べられるようになったのは、〇〇大学の水産学部のおかげでも、すしざんまいのおかげでも、八戸漁業協同組合の努力によるものでもない。松本先生が脳研究をされる過程で生きたイカの神経を使うために、それまで不可能だったイカの生けすを実現したからなのだ。
脳研究の歴史でみると、ちょうど分子レベルでの脳の構造がほぼ明らかになったというタイミングでの連載だった。かなり踏み込んだ解説なので、このあと紹介する3冊に比べていま読むとクラクラするような内容である。脳のフィードフォワード処理や新皮質を構成する「コラム」(後述)は部位によらず同じなので、そのメカニズムがわかればコンピューターにできる可能性があるとも書かれている。
この時点で日本は脳の計算理論の研究で進んでおり、それを工学的に作ってしまおうというのが先生の研究だった。当時、動作しながら自身を書き換えていく「進化するハードウェア」(Evolable Hardware)としては、遺伝的アルゴリズムとFPGAを組み合わせたものが主流だった。自動的に組みあがる回路に学習性を与えれば脳はできあがるはずですとある。
その松本先生が、2003年に、62歳で多くの仕事をやり残したまま他界されてしまったのは惜しいとしかいいようがない。
《脳型コンピューター》、あるいは《脳》とつながるコンピューターは、いままでの箱に入った計算機械の延長としてのコンピューターという装置とはまったく別のパラダイムのコンピューターになる可能性がある。つまり、思いもよらないものがひょいと出てきそうで楽しい。すでにスマホに入っているニューロチップはそれを予感させもるものかもしれないが。
そんな私の《脳とコンピューター》についての気分をがぜん刺激する本が、昨年末から今年にかけてたて続けに出てきた。少し時間もたっているのですでに読まれている人もいると思うが、3冊ほど紹介させてもらうことにする。
ビジネスマンもSF小説を書く人も哲学者も
ここらで常識をアップデートしよう
『脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか?』(紺野大地・池谷裕二著、講談社)は、ズバリ《脳の改造》についての本だ。脳の改造って、マッドサイエンティストっぽく聞こえるかもしれなが、脳とコンピューターをつなぐことはすでに始まっている。
池谷裕二さんには、ザリガニとザリガニの脳をつなぐお話をうかがったことがある(『別冊アスキー』2010年1月刊行のインタビュー「脳の世界とコンピュータの世界が近づいている」)。脳はリズムをもっていて、コンピューターを介してハブになる神経細胞をうまくつないでやると同期するというお話だった。さらりと、「コンピューターを介して」といわれたときにピクリときたのを覚えている。
興味深いのは、著者らが当たり前だが明確な方向性をもって研究をすすめている部分だ。ヒトが、文字やことばを使うようになったのは《脳の使い方》が拡張されたということだ。それらは、筆記具や電話やインターネットといった《道具》を使うことによって実現した。ならば新しい道具が開発されれば、まだまだ我々の知らない脳の能力が引き出せるはずである。そして、ここでその道具とは《AI》(いわずもがなそれを動かすコンピューターを含む)だというわけだ。
2020年、皮質脳波計というシート状の電極を使った衝撃的な研究結果が報告されたそうだ。それは、視覚野を線でなぞるように電気刺激することで《脳で文字を読む》ことができたというものだ。電気刺激することで目を介さずに文字や風景を見ることができる。与える電気刺激のためのデータは、指でなぞるのではなく、撮像素子を使った人工的な目でもいいし、バーチャル空間の風景みたいなものでもよいはずだ。
同じように、音や匂いや味覚のセンサーを電気信号に変えて皮質脳波計のインプットにしてやることも考えられる。「《耳を介さず脳で聞く》《鼻を介さず脳で嗅ぐ》《口を介さず脳で味わう》といった世界が待っているかもしれません」。あとはレゾリューションの問題。これが実現されたら「家の中にいながらまるでハワイのリゾートホテルにいて、おいしいパンケーキを食べているように感じる」ことが可能になるかもしれないと書かれている。
それは、《映画『マトリックス』の世界観にかなり近いといえる》などとも書かれている! これをとっかかりに、「脳にAIを埋め込んだら」「脳をネットに接続したら」、「たくさんの脳を繋げたら心はどう変わる」など、そして、その先はどんな世界が待っているのか? と本書は、読んでいるこちらも想像力をかきたてられるところが、めちゃめちゃ面白い。
脳とコンピューターやネットワーク技術、AIなどが混然一体となって、人類は次のステージに立つことになるのではないか? ビジネスマン、SF小説、哲学や思想系の方々にも読んでほしい一冊である。
脳の中には《座標系》がある! Palmの考案者ジェフ・ホーキンスが脳研究に重大なヒントを与えている
1990年代からデジタル分野をご覧の方なら、それまでのPCなどのコンピューターに加えてモバイルデバイスが登場してきたのをご存じだと思う。日本国内なら電子手帳からシャープのZAURUS、米国ではアップルのニュートン MessagePadなどが登場。その中で最も成功したのが、1996年にパーム社が発売したPalm(初期にはPalm Pilot)とPalmOSを搭載した他社を含む製品群(VisorやソニーCLIE)だった。
なぜPalmが成功したかといえば、《Zen of Palm》という言葉に象徴される設計思想に貫かれていたからだとされる。持ち歩いてバッテリで動作させるものである以上ハードウェアのスペックは絞りきる。そのうえで、何でも使いたい機能を突っ込むのではなくひたすらシンプルな道具とする。これによって、2002年にPalmOSを搭載したモバイル機器は、本家Palm社だけで累計2000万台を突破したとある。
このPalmを率いていたのが、その創設者であるジェフ・ホーキンスという人物である。今回紹介する2冊目の本、『脳は世界をどう見ているのか 知能の謎を解く「1000の脳」理論』(大田直子訳、早川書房刊)の著者は、ジェフ・ホーキンス。まぎれもない、同一人物によるものである。
ジェフ・ホーキンスは、インテルに入社後に脳の研究をやりたくて大学をあたったが、彼の考えは先を目指しすぎていて受け入れられなかった。そこで、ちょっとアルバイトのつもりみたいな感じでPalmを作っていたらしい。液晶1枚に最小限のボタンからなるPalmのスタイルは、その後のiPoneに引き継がれたといってもよい。そもそも、スマートフォンの元祖の1つが、やはりPalmのTreoだ。
彼は10年間、モバイル機器とOSの仕事をしたあとスパッとコンピューター業界をあとにして、脳研究のための私設の研究所を設立する。もし、Palmを彼が続けていたらスマートフォン時代は違った形で訪れていただろう。しかし、彼が、何度かに渡って発表した脳研究の成果のほうが、人類の歴史というスケールから見れば大きいのかもしれない。
本書は、彼の脳研究の全貌を知ることのできる一般向け解説書である。脳の活動については世界中の研究者によって膨大な論文や報告がされているが、《知能》を脳がどうやって生み出しているかはまるで解明されていない。脳の仕組みはまったく謎のまま。とくに足りないのは実際に起きていることを解釈する考え方の枠組みであった。
まさにここに切り込んだのが、ジェフ・ホーキンスの研究である。人間の脳の7割を占め、視覚、触覚、聴覚、言語、数学や哲学のような抽象的思考まで、知能と結びつくものすべてをつかさどっているのが新皮質である。その仕組みについて、同じ原理で動く知的機械をつくれるくらい詳しく理解することが彼の研究の目的だそうだ。
我々の新皮質は世界をモデル化する15万ほどの《コラム》とよばれる部分からなる。このコラムはヒトが何かするときに同時に複数の予測をする。新皮質による予測には2種類あり、1つは自分のいる空間や音楽のメロディーなど環境に対してであり、もう1つは、自分が何かを手にとるなど行動をとったことに対してである。これはある意味とてもシンプルな現象で、ニューロンの樹状突起活動電位によって細胞体の電圧が上昇することが予測なのだ。ホーキンスは「位置について、用意…」ときて「ドン」を待っているような状態と書いている。
複数のニューロンが同じパターンの入力に反応するが、予測外のときはすべてのニューロンが発火、予測された入力なら予測状態のニューロンだけが発火する。これをメロディのようなシーケンス記憶についてコンピューター上で検証したところ、わずか2万のニューロンが何千という複雑なシーケンスを学習することができた。また、ニューロンの3割が死んでも、雑音だらけでも働き続けるといった驚きの結果となったそうだ。
しかし、ホーキンスの研究で最も重要と思われるのは《座標系》についての発見である。たとえば、指を動かしてコーヒーカップのようなものをつかむとき脳は何を知っていれば予測できるか? 1つは、カップに対してあくまで相対的に指がどこにあるか。指が知りたいのは《物体上の位置》だ。これは、カップに付随する座標系が脳の中にあることを意味する。カップと同じようにイスにも付随する座標系がある。そのため椅子が向きが変わっていると座標系も回転してなんなく座ることができる。
脳は、座標系によって物体全体をいちどに処理できる。たとえば、自動車の座標系が脳にあれば、自動車のあらゆる特徴を回転したり、引き伸ばしたりできる。ここで重要なのは、新皮質のコラム内のニューロンの大部分が座標系をつくって位置を追跡するタスクを行っているということだ。
もうひとつ、座標といえば環境に対する自分の位置を把握するというはたらきがある。脳の古い部位(哺乳類では海馬と嗅内皮質)には訪れたことのある場所の地図を学習する「場所細胞」というものがある。さらには、それを地図のように記録する「格子細胞」というものもある。新皮質が巨大である理由は脳のほかの部位と異なりあるとき一気にできあがった。そのスピードを可能にしたのは新皮質のコラムは同じものの大量のコピーでできているからである。実は、海馬と嗅内皮質を最小の形態にしたものを何万もコラムの中に並べたものが新皮質になったと考えられる。
その新皮質のコラムは2層のニューロン群からなっていて、上の層が感覚を受け付けて発火(本書の説明では街の中で噴水を目にする)。噴水のような観察された特徴が町のどこにあるか地図にあたる下の層の座標系に関連していく。下の層は、およそ格子細胞なのだ。これによって我々は街の風景を予測しながら歩くことができる。これに関してもホーキンスらはコンピューター上で検証、個々のコラムが何百ものモデルを学習できることを示した。これが書かれた2019年の論文は、感覚運動体の《認識の理論》だが、問題はここからだ。
新皮質がコラムからなることは、1950年代に米国の神経生理学者ヴァーノン・マウントキャッスルによって発見された。新皮質が同じような組織の繰り返しであるということは、それらが同じようなアルゴリズムで動作するに違いないとマウントキャッスルも考えたそうだ。ホーキンスは、このコラムの具体的な仕組みや動作原理を解明していったのだといえる。
重要なのは、人々が新皮質で行うことはコーヒーカップを手にとったり、町を歩いて噴水を見つけたりするだけではないということだ。視覚、触覚、言語、哲学といったさまざまなこと、すなわち《座標系》とはおよそ無縁に見える知的活動などをふくめてすべての新皮質にかかわる脳活動が、基本的に同じ《座標系》にもとづく動作原理にしたがっているということである。
これ以上、私が、本書の内容をつまんで紹介しても正確に伝えることにならないのでこのあたりにしよう。1つ付け加えるとすれば、この本の醍醐味は、ホーキンスの脳理論の中身もさることながらそこにいたるきったけとなった生活の中の出来事まで語られていることだ。それは、まさにモバイル端末に関して世界中のメーカーがひしめきあっていた1990年代に突出してビジネスを成功させた、彼の抜群のインスピレーションとセンスを思わせるものがある。
脳研究のなかでもハードプロブレムだと指摘されている《意識》についても、ホーキンスは、明確に考えを示している。「意識があるという状態には記憶が必要」(まさに意識がなかったの反対の状態)であり、「その時々の思考の記憶が形成されることが必要」(それがないと何を考えているのかわからなくなる)。いわれてみれば、そのとおりなのだがこれらが彼の脳理論から大きく離れることなく語られるところがポイントである。
存在しているという意識の中心部分は、そうした記憶を形成しながら過ごすあいだにそれを再生することに依存している。さらにはそうした状態を機械に持たせることはできるかと問われれば、それはありだとポンと答えしまっているところが凄い。しかも、量子効果や未知の物理法則でしか意識は説明できないんじゃないかとしている研究者にたいして、理由を示せと迫っている。
噴水を見て新皮質の中の地図とてらしあわせるというくだりを読んでいて、私は、自分の生活の中で思い当たるフシがあった。建物が壊されて新しいビルができると、わずか数か月前までそこにどんな建物があったのか思い出せない。これは、私が歳とったからではなくて若い人でも同じことを不思議がっていう。私の頭の中の格子細胞のたとえば文京区の地図は決まっているから、新しい建物に書き換えられたために出てこないのだろうか。
この話、こんなシンプルな理解でよいのだろうか? ほかの知的活動も同じ原理だとすると、忘れないためには同じ座標上を書き換えず横にならべるなり高層化するなりするのがよいことになる。
リストバンドで《音》を聴くベンチャーCEOは
ベストセラー脳本の著者
残りの1冊は、実は、まだ読んでいる最中の『脳の地図を書き換える 神経科学の冒険』(デイヴィッド・イーグルマン著、梶山あゆみ訳、早川書房)だ。デイヴィッド・イーグルマンといえば、米国の神経科学者で『あなたの知らない脳 意識は傍観者である』(大田直子訳、早川書房)などの著者であり、BBCなどで放送された脳のドキュメンタリー番組のホストとしても活躍した人物である。
本書のタイトルを見れば、すぐに冒頭で触れた脳が《学習して自分を書き換えながら動いている》というストーリーにつながるものだということがわかるだろう。著者は、《ライブワイヤード》(原著の書名がこれだ)という概念を提唱するとともに、それを一歩進めることで五感以外の感覚を生み出すことや、身体を外部に拡張することが可能になるとしている。つまり、『脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか?』の内容とも関係してくるものとなっている。
「ニューロンは生存競争に明け暮れている。隣り合った国どうしのようにニューロンも自らの領土を主張し、それを執拗に守ろうとしている。領土と生存を賭けたこの争いは脳というシステムのあらゆるレベルで起きていて、ニューロンやニューロンの間の接続ひとつひとつが資源を求めて競いあっている。境界をめぐる戦いが脳の生涯を通して熾烈に繰り広げられる」というあたりは、まさに脳がライブワイヤードな装置であるという生々しさを感じさせる。
しかし、それにもましてこの本で気になるのは、イーグルマンが、そうした脳と外部を人間の知覚以外の方法でインターフェイスする装置を作るベンチャーのCEOであることだ。2015年に設立されたネオセンソリー社(Neosensory)のコンセプトは、TEDの「Can we create new senses for humans?」 (人に新しい《感覚》を作ることはできるか)でご覧になった人もいるかもしれない。
《感覚置換》のための装置として、聴覚障害のある人が皮膚の振動を介して聴覚情報を認識できるようになるという《ベスト》が紹介されている。体感ゲームのための振動ベストみたいなものが《BMI》(ブレイン・マシン・インターフェイス)になると言われると「えっ?」と反応したくるが、現在、ネオセンソリー社のサイトを見るとFitBitの活動量計みたいな《リストバンド》に進化している。なんと、リストバンドの形をした補聴器や耳鳴り軽減デバイスを発売しているのだ。
聴覚に限定されているとはいえ、誰でもすぐに使いだせる《非侵襲的》なインターフェイスがどこまでいけるのかは興味深い。脳は非常に柔軟に変化に対応するため五感以外の感覚を得ることができるというのもありうるのだろう。身体を外部に拡張することについては、東京大学大学院の稲見昌彦教授による取り組みに通ずるものだと思う。個人的に、最近、人の声が聴き取りにくくなっているので、ネオセンソリー社のリストバンド型デバイスを試してみたいと思ったが、この原稿を書いている時点では日本に代理店はないようだ。
これからのAIや脳研究とメタバースやミラーワールドは
密接にかかわってくる?
ジェフ・ホーキンスの本を読みかけたところで、すぐに連想したのは今日のディープラーニングの盛り上がりの立役者であるジェフリー・ヒントン氏がいま主張していることだ。彼は、「カプセル」というものを提唱しているが、これは画像認識において構成するパーツの空間的な位置までもあつかうためのものだという。カプセルネットワークによって、すでに見たことのある物体を違う視点から見たもである場合にそのように認識できる。
これは、ホーキンスの《座標系》によって物体の見る角度が変わっても同じモノだと認知できるしくみを思わせる(椅子の向きが変わっても同じ椅子と認識できるという例をあげた)。案の定、本を読み進めていくと座標系の重要性を理解しているAI科学者のひとりが、ジェフリー・ヒントンだと書かれていた。ヒントンは、現在のディープラーニングには位置の概念が欠けているために世界の構造を学べないと批判的になっている。
たしかに、この2つは目指すところが似ていて、将来のAIは、ヒントンが考えだしたカプセルネットワークが主流となるのか、それともホーキンスの研究による脳の格子細胞のメカニズムを生かしたものになるのか? まだわからないが、いずれすにしろ知能に《座標系》は必要であるとホーキンスは書いている。
それでいまさらながら思うのは、文字どおりの座標系によって成り立っているのが、いまやバラエティ番組でも取り上げられるようになった《メタバース》の世界だということだ。我々のいる世界全体をデジタルツインの発想でまるごと作ってしまう《ミラーワールド》がその先には控えている。
ホーキンスの脳理論や新しいAIが必要とする座標系のデータを、VRChatやUnityを使う人たちが、日々作りだしている。これらいまはまったく別々のものに見えるトピックが、あるときパシッと音を立てるように反応する一歩手前の状態にいまはあるのではないか? それは、ヒトの心や存在そのものと世界とのかかわりまでも変えてくれるのではないか? などと妄想したくなる、いくらか新型コロナの影響が和らいだ2022年の夏を迎えようとしている。
遠藤諭(えんどうさとし)
株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。「AMSCLS」(LHAで全面的に使われている)や「親指ぴゅん」(親指シフトキーボードエミュレーター)などフリーソフトウェアの作者でもある。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。その錯視を利用したアニメーションフローティングペンを作っている。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。東京MXTVにて放送中のDeepTV.artに出演中(YouTubeでも視聴可能)。
Twitter:@hortense667
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります