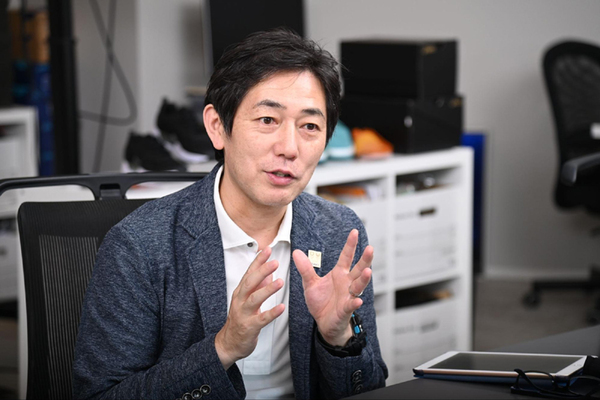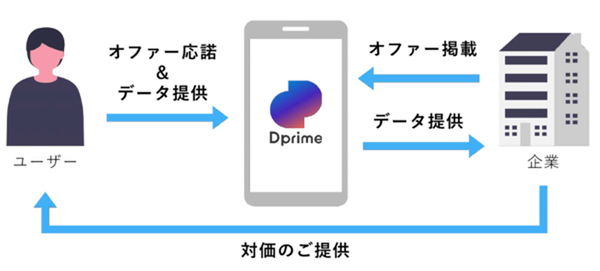株式会社アシックス 執行役員 スポーツ工学研究所長 原野健一氏×株式会社ORPHE CEO/Founder 菊川裕也氏
スポーツ業界や健康を支える新しい価値創出をスマートシューズから実現したEVORIDE ORPHE
2021年08月27日 07時00分更新
この記事は、民間事業者の「オープンイノベーション」の取り組みを推進する、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会(JOIC)との連動企画です。
2020年に発売開始された「EVORIDE ORPHE」は、足の動きをデータ化し、ランナーの走り方の特徴を可視化することで目標達成をサポートするこれまでになかった製品だ。アシックスのランニングシューズに、スタートアップ企業ORPHEが開発したセンサーを搭載したスマートシューズはなぜ実現できたのか、協業の背景を聞いた。
“モノとコトを連動した新しい体験”にまつわる新市場開拓
| 実施内容の要約 | スマートシューズ分野を牽引するスタートアップと日本を代表するスポーツメーカーによる協業(ORPHE・アシックス) |
| 関わり方や提供物 | スマートシューズとそれに関連したセンサー技術面での協力、製品デザイン(ORPHE) 成長のための出資、シューズ本体の生産技術やデザイン協力、「EVORIDE ORPHE」販売(アシックス) |
| 求める成果・ゴール | AIによるパーソナルコーチングの新市場の開拓、価値あるデータの創出(ORPHE・アシックス) |
| 将来 | スマートシューズによる新しい価値や市場の創出(ORPHE) 他のスポーツへの応用や、医療や保険との連動、新たな商品開発といった他分野への応用によるさまざまな社会課題の解決(アシックス) |
2020年7月にクラウドファンディングサイト「Makuake(マクアケ)」で予約販売し、同年12月にアシックスの一部直営店およびアシックスオンラインストアで発売開始された「EVORIDE ORPHE」は、アシックスのランニングシューズ「EVORIDE」のミッドソール内部に、スタートアップ企業の株式会社ORPHE(旧社名:株式会社no new folk studio)が開発した専用センサー「ORPHE CORE 2.0」を搭載したスマートシューズ。
履いて走るだけでランニング中の足の動きをデータ化し、ランナーの走り方の特徴を可視化することで目標達成をサポートする。走行中の距離、ラップタイム、ペース、ストライド(歩幅)、ピッチ、着地エリアや時間、接地角度、着地衝撃などのデータを取得し、それらのデータとアシックススポーツ工学研究所の知見を組み合わせ、走り方の評価スコアを算出する。
EVORIDE ORPHEは、2019年に「ASICS Accelerator Program(アシックス・アクセラレーター・プログラム)」での最優秀賞受賞を大きなきっかけとして、およそ3年にわたる共同研究・共同開発の末に2020年12月に発売。2021年2月には、スポーツ庁「INNOVATION LEAGUE コンテスト」で大賞を受賞するなど大きな注目を集めている。
2社の取り組みがどのような背景で結実したのか、プロジェクトを進めた株式会社ORPHEの菊川代表と株式会社アシックス執行役員 スポーツ工学研究所長の原野氏に話を聞いた(以下、文中敬称略)。

株式会社ORPHE CEO/Founder 菊川裕也(きくかわ・ゆうや)氏
一橋大学商学部経営学科を卒業後、首都大学東京大学院にて芸術工学を専攻。2014年より新しい音楽演奏用インタフェースの研究として開発を始めたスマートフットウェア「Orphe」の製品化をきっかけに株式会社no new folk studio(現 株式会社ORPHE)を設立。「表現のためのIoT」をキーワードに新製品を提案していく。グッドデザイン賞受賞、文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品選出、スポーツ庁INNOVATION LEAGUE コンテスト大賞受賞 等。

株式会社アシックス 執行役員 スポーツ工学研究所長 原野健一(はらの・けんいち)氏
1992年4月株式会社アシックス 入社。スポーツ工学研究所にてFW(フットウェア)の材料設計に従事。2000年に中国広州事務所赴任し、アシックス材料のOEM工場(生産委託工場)への移管や技術指導のほか、OEM工場に品質試験設備を導入し、その標準化を行なう。新規材料移行システムも構築。2009年に再びスポーツ工学研究所に配属となり、機能性材料の開発を担うチームや部を先導。2014年にフットウェア機能研究部長の経験を経て、2018年から現任である執行役員スポーツ工学研究所長を務める。
アクセラレータープログラムに至るまでの“紆余曲折”
──それぞれのご紹介と協業に至るきっかけについて簡単にお聞かせください。
原野 まずアシックススポーツ工学研究所のミッションからご紹介すると、アシックスの主要な3つのプロダクトである「シューズ」や「アパレル」、「エクィップメント」に対してスポーツで培った知的技術を通して、みなさんに新しいライフスタイルを提供したい、というビジョンのもと研究・開発を行なっています。この3分野、かつてのアシックスではモノというかたちでの提供に限っていました。現在はプロダクトだけでなく新しいサービスや体験を提供する、ということも研究対象として、開発を進めているのが当研究所です。
菊川 我々は2014年の創業以来ウェアラブルインターフェースの開発に注力しており、2016年には「ORPHE ONE」というスマートシューズを発売しました。そこからランニングなどにおけるセンシング分野に注力しはじめて2018年には「ORPHE TRACK」を発表し、アシックスさんのアクセラレータープログラムに応募したところ、我々のシューズを採用してもらったのがきっかけで「EVORIDE ORPHE」の共同研究・共同開発がスタートしたのです。

2016年発売のORPHE ONE(販売終了品)
https://ascii.jp/elem/000/001/216/1216645/img.html
──取り組みからおよそ3年で製品販売に至ったというのは、ものづくりとしてかなり順調だったのではと見受けますが、いかがですか。
原野 確かに、時系列だけで見ると順調に進んでいるように見えるかもしれませんが、実際にはかなりの紆余曲折があってここまでたどり着いているんです。
じつはもともと菊川さんと、こういうことをしたいねと取り組みをスタートしたのは、もっとずいぶん前からで、「モノとコトを連動した新しい体験を創出したい。それがこれからのスポーツ業界や健康を支えるうえで重要なものになるだろう」というのはお互いにずっと思っていたことです。しかし当時はまだ、そういう思いだけでは組織として動くとなると総論では賛成ではあるけれど、実現までとなるとすごく時間がかかっていたんです。実はアクセラレータープログラム以前から、“こういうことをしたい”と、社会実装の実証実験という形で、会社にも数回提案していたのが実状です。
ORPHEさんとのアクセラレータープログラムの前にも、2回ほど“モノとコトを連動した新しい体験の創出”に関わる具体的な取り組みを行なっているんです。
ひとつは社会実装のところで、三菱UFJ信託銀行さんが提供する情報信託プラットフォームの実証実験がありました。ふたつは“光るシューズ”へのインスパイアです。アシックスにはGELという透明な緩衝材があるのですが、それを靴底全体に使った「GEL-QUANTUM INFINITY」という商品を2018年12月にローンチしました。なんとかこのシューズをお客さまに認識してもらいたい、新商品を認知してもらいたい、という思いから、ローンチイベント用に靴底全体が光る専用モデルを共同開発し、ダンサーさんが踊りながら“光の演出”を行ないました。
こうして社内のなかでも少しずつ“モノとコトを連動した新しい体験”に対する認識度が上がっていってのですが、やはりこれまでのようなボトムアップよりも、トップダウンによるアプローチのほうが業務として進展しやすいだろうということで、アクセラレータープログラムとして、菊川さんと一緒に進めていくこととなったのです。
三菱UFJ信託銀行の実証実験への参加で関係が深まる
──アクセラレータープログラムに応募する以前、ORPHEではどのようにスマートシューズへの取り組みを進められていたのでしょうか。
菊川 ちょうど2018年、我々のスマートシューズにまつわる技術の原理ができあがったばかりというタイミングでのアクセラレータープログラムのスタートとなりました。それ以前までかなり試行錯誤していたのです。
最初の頃は、ハードウェアレイヤーとしてシューズにセンサーやコンピュータを埋め込んで履けるというモノと、そこからスマホとリアルタイムに無線通信するネットワークの部分に注力しました。いわば家電製品を常に踏みつけているようなものなので、ハードウェアレイヤーでもかなり無茶をする製品と言えますから、どうやったらそういうものができるのか、技術の確立までかなりの時間がかかりました。
そこを一応乗り越えてから、光るシューズという面白い製品ができたのですが、それでも、機能性や耐久性、通気性、といったシューズとしての機能面とファッションや値段、物流など、大企業であれば当然にできるようなことも、我々のようなイチからのスタートしているベンチャーにはなかなか厳しいのだと思い知った時期がありました。そうしたなか、いろいろとシューズメーカーと話をするなかで、アシックスさんとの出会いがあったのです。
結論から言えば、「一番いい形で世界に対して勝負ができるのがアシックスだ」と判断し、我々としてもかなりアプローチしていきましたね。国内でスマートシューズによる新しい価値創出に向けた意思決定ができて、研究所があって、開発から製造までできるシューズメーカーというのが、そもそも限られているうえ、かつ世界に対して勝負しているメーカーとなるとアシックス以外にないのでは、というのが正直なところでした。自分たちにとってのシナジーという面ではアシックスさんは明確に持っていましたので、まずは関係性を結んでもらえるようなレベルに我々がなれるようにと、だいぶ遠いところからのスタートだったという思いがあります。
──アシックス側ではORPHEとの協業に至るまではどのような動きや判断があったのでしょうか。
原野 アシックスでは、1949年の創業以来、創業者の理念をDNAとして受け継いでいます。とりわけ1977年に社名の由来にもなっている“健全な身体に健全な精神があれかし”という創業哲学をすごく大切にしているんです。世間でも健康意識がより高まっているなか、それに対する新しい価値を提供するためには、やはりスタートアップのスピード感やトレンドに対する敏感さなどが求められました。
そうしたなかでお互いの関係性に大きな進展を見せたのが、さきほど述べました2018年11月に行なわれた、三菱UFJ信託銀行さんの実証実験への参加でした。シューズにセンサーを入れて、無意識な歩行動態を認識して情報銀行としてパーソナルデータ連動させるサービスというのを研究したのですが、事業化までは進めませんでした。
ただしここでの成果が、社内でもスマートシューズやスタートアップとの協業がもたらす価値を感じてもらえることに大きく貢献することとなったのです。
CES 2020への参加が大きな転機に
──そうした紆余曲折の末に「EVORIDE ORPHE」を製品化したいま、開発の経緯を振り返って感じることは何でしょうか。
菊川 振り返ってみれば、かなりのパワープレイだったなというのが正直なところです。自分のなかでは、せっかく会社から背中を押してもらっても、それでも社内ではまだ、できるのかできないのか、といった迷いのようなものが、実証実験の段階では感じられたので、今度こそアシックスとORPHEの協業によるプロダクトとしてしっかりと世に問いたいという強い思いがあって、突き進んできました。
特に大きな進展を見せたのは、CES 2020への参加からでしょう。そこから1年以内で発売まで行けたというのには、“大急ぎ”の側面もあったのですが、それは過去数年間の協業や研究の積み上げがあって、そこで問題点をある程度共有・把握できていたからこそ可能だったのです。まさに、CES以前のさまざまなプロジェクト全体が製品化に至るプロセスだったのだと思っています。
原野 言われたようにCESでの成功があり、商品化を早期に実現したいと考えたのですが、やはり、この商品がお客様に受け入れられるのかという点について、社内全体のコンセンサスを取るのはなかなか難しかったです。そこで、受注販売の形式が適用できないかと考え、クラウドファンディングの活用を検討しました。社長に相談したところ、新しい試みに賛同してもらい、関係者を集めたキックオフミーティングも開催しました。その会議の冒頭で、関係者各位が連携し、商品化に向け加速するようにとのコメントをトップから得られたからこそ、短期間で商品化につなげることができたと考えています。
──最後に、オープンイノベーション全般や、今後求められる意義や価値に対するお二人の考えをいただけますか。
菊川 これまでの取り組みを振り返ってみて、協業ノウハウとして少し思うのは、スタートアップであれば取れるリスクでも大企業にとっては取りづらいリスクであったり、逆にスタートアップにとっては苦手でも大手であればすでに機能を持っていたりするので、そのような役割分担の最適化を図って行くことができると良いのではということです。そのためにはお互いの狙いや弱みを含めて共有していけるような信頼関係の構築が重要だと感じています。
そして一般的かもしれませんが、やはりイノベーションがなければ競争力は維持できない、イノベーションが必須であるという考え方と、テクノロジーの方向性に対するビジョンの一致、というのがオープンイノベーションの前提になるのではないでしょうか。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)という言葉もさまざまなところで言われていますが、一部の業務をデジタルで効率化する、という発想ではなくて、あらゆる産業がデジタルを基盤としていくときに、自社の仕事がどのように変化して行くのか、そのときに価値を発揮するためにどのようなポジジョンを取るべきなのか、といった戦略がまず必要です。そこを共有した上で、それぞれの強みを発揮していけるような取り組みこそが、オープンイノベーションへとつながって行くのではないかと思っています。
原野 社内外の要素を効率的に活用し、イノベーション──つまり新たな価値を、スピード感を持って創出する事にオープンイノベーションの本質はあると認識しています。そして今後は、個人に最適化された価値の創出、さらには、継続した価値の進化と深化が重要となっていくのではないでしょうか。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります