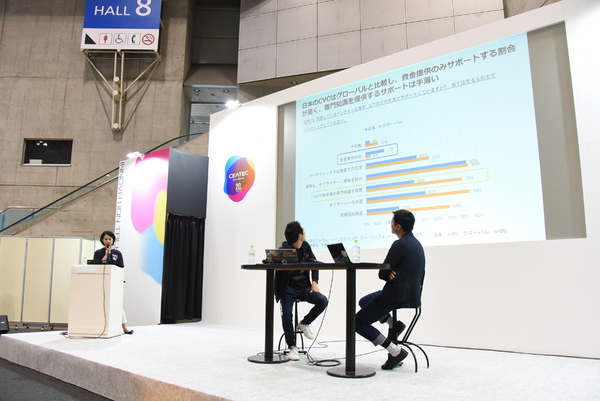CEATEC 2019セッション「STARTUPs×知財戦略~CVCを通じた知財の共創~」レポート
出資増えるCVCにベンチャーが求める役割とは
2019年11月14日 16時00分更新
特許庁は2019年10月15日、幕張メッセで開催された「CEATEC 2019」のイノベーショントークステージにてセッション「STARTUPs×知財戦略~CVCを通じた知財の共創~」を実施した。近年、日本でもCVCによるベンチャー投資が増えている。事業会社と支援先ベンチャーが共に発展するためにはベンチャーの知財を成長させることが重要だ。単なる資金提供に留まらない、CVCに求められるベンチャー支援の形とは。
パネラーには、エアロネクスト中畑稔取締役CIPO、リアルテックファンド代表でユーグレナ取締役副社長の永田暁彦氏が登壇。モデレーターは、特許庁 企画調査課 スタータップ支援チームの進士千尋氏が務めた。
日本のCVCはベンチャーの知財戦略をもっと支援してほしい
最初に特許庁の進士氏から、知財戦略における投資家の果たすべき役割と、日本におけるCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の動向を説明した。
知財戦略は、経営戦略の中で知財をいかに活用するかを決めるものだが、研究開発型ベンチャーのCEO、CTOは、技術に視点が偏りがちで、どのように知財を守るかという観点から知財戦略を考えてしまう。また知財専門家は、技術をどうやって権利化するかに視点が偏り、必ずしも経営に観点を持っているわけではない。そこで、経営全体が見える投資家の視点からアドバイスをすれば、スタートアップはより成長できるのではないだろうか。
世界の投資の動向として、近年はCVCからの投資が増加しており、日本においても事業法人からの投資額が伸びているが、日本のCVCは約9割が2010年以降に設立されており、経験が浅い。米国の調査データによれば、CVCから出資を受けた企業は、一般のVCから投資された企業に比べ、投資後の特許件数が増えており、この原因は、CVCからの知財面でのサポートによるものではないかと分析されている。一方で、日本のCVCはグローバルに比べて、資金提供のみをサポートする割合が高く、専門知識を提供するサポートは手薄い。加えて、日本のCVCは投資判断時においても知的財産の評価は必ずしも十分とはいえないようだ。CVCはどのようにベンチャーと付き合っていけば、ベンチャーのポテンシャルを引き出し、成長を後押しできるのか。
トークセッションでは、中畑氏はCVCから支援を受けるベンチャー側の立場、永田氏はベンチャー、投資家の両方を経験した立場から、CVCに持ってほしい姿勢、CVCに期待する投資先への支援、CVCの投資目的の3つのトピックについて議論した。
CVCにもってほしい姿勢
進士氏(以下、敬称略):お二人は、CVCのこういうところは困った、あるいはこういう支援が助かった、という経験はありますか。
永田氏(以下、敬称略):姿勢というよりも、CVCにはベンチャー投資のプロになってほしい。ユーグレナは今、出資をする側になっていますが、成功しているCVCに一貫しているのは、お金や契約でベンチャーを縛っていないことです。成功しているCVCが大事にしているのは、ブランドや人間関係。ベンチャーは、経営者が10年、20年たっても変わりませんが、大企業の担当者は数年で代わることがほとんど。そのため大企業は、人が変わっても企業間の関係性を維持できるように契約で縛ろうとしてしまう。ベンチャーとの関係性を築くには、まずその意識を変えないといけない。新しい事業、新しい文化の中にきちんと対応していくためには、CVCには、内部人材だけでなく、外部から投資のプロフェッショナル、起業経験者を取り込んでいくことも必要ではないでしょうか。
中畑氏(以下、敬称略):エアロネクストもCVCから出資してもらっていますが、資金提供だけでなく、大企業のもつ経験、経験に基づくリソースの部分にも期待しています。例えば、エアロネクストの場合、自社での大量製造は難しい。先日提携した小橋工業株式会社は、マスプロダクションのノウハウとリソースを持っている。そこで、ドローンの試作モデルを実体化するとき、どのような問題があるか、といった経験に基づくアドバイスがもらえるのは大変ありがたいと思っています。お金以外の部分で何をサポートできるか、という姿勢をもってほしいですね。ただし、個人的には、いろいろなCVCがあっていいとも思っています。スタートアップ側でも、お金だけ出資してもらうのがいい場合もありますし、目的をもって株式を持ってもらいたい、という場合もある。そのミスマッチによって、齟齬が生じているような気がしています。
CVCに期待する投資先への支援
進士:日本は、お金だけをサポートするCVCが多いというデータがあります。CVCからこういう支援が受けられて助かった/こんな支援があると助かる、というのはありますか?
永田:ユーグレナにとってJXTGホールディングスさん、日立製作所さんとの資本提携は非常に意味のあるものでした。アカデミアスタートの研究開発ベンチャーにとって、メーカーとしての研究開発の姿勢を彼らから徹底して教わりました。一方で、僕たちが提供したのは、アントレプレナーとしてのチャレンジやスピード感だと思っています。機能的な共有というよりは、姿勢や考え方の共有が大きかったですね。それが僕たちの今の研究基盤のベースになっています。
進士: CVCが支援を提供する際に注意すべきポイントはありますか?
永田:CVCが注意しないといけないのは、出資に対する対価は株式シェアだけだということ。それ以外の権利や特別な条件が付随した瞬間、すべての投資家に対して不利益になる。共同研究や事業提携と資本提携は独立した関係であるのが大前提です。投資を受けたからといって、何らかの条件や支援があるのではなく、その先はすべて個別事象として交渉することです。大企業との共同研究では、知財のシェアについてきちんと交渉する姿勢はスタートアップ側にももってもらいたいですね。
中畑:ベンチャーにとって、お金のプライオリティーはいちばん高いけれど、それに加えて、こういうこともできるよ、という提案があるとありがたいですね。例えば、バックオフィスチームが足りないときに人材を派遣してくれたりすると、創業初期にはすごく助かります。株式を渡す以上に、彼らからノウハウ、人材、リソースをいただけるので、出資してもらいたい、という気持ちが強くなります。ベンチャー側が出資先を選ぶというのはおこがましいけれど、選ぶときの決め手になるのは確かです。
CVCの投資目的
進士:事業会社としては共同研究開発等をすれば、ある程度、お互いに与えるもの/得られるものがあるなか、あえてCVCとして投資をする⽬的はなんでしょう︖
永田:一番の目的は、旗を立てること。正直、ベンチャー側としては、ノウハウや知財戦略の支援よりも、まずはお金がほしい。ベンチャーから大企業にはなかなかアプローチができないため、それを明示するために大企業がCVCを持つことは有効です。
進士:ベンチャーに直接投資するという形をとらなくても、例えばリアルテックファンドに出資して、ベンチャーに対してオープンマインドですよ、という姿勢を見せるだけでもいいのでしょうか?
永田:大企業をひとつの個性でくくることに限界があると思います。連携する対象として、技術という領域では、自分のやっている研究領域と近い会社を探索している会社もあれば、不得意な分野の会社と連携したいと考えている企業もあります。そのどちらにも当てはまらず、アントレプレナーを収集する目的でCVCをやっています。ただし、事業面でのリターン(ストラテジックリターン)があれば、ファイナンシャルリターンはなくていいという発想になるのは間違いです。CVCは、常にストラテジックリターンとファイナンシャルリターンの両方追わなくてはいけない。事業連携できればいい、という発想では、パフォーマンスが落ちたときに、CVCの継続性が危うくなり、担当者の交代やベンチャーとの関係性まで変わってしまうからです。情報収集だけなら、ファンドに出資するだけでも目的を達成できるでしょうし、大企業側が目指すものによって関係性は変わるものです。
中畑:おっしゃる通り、CVCによって聞いてくる観点や深さ、我々に求めている点がぜんぜん違いますね。知財という面では、投資判断の基準以上のことまで深く関心をもたれるCVCもいらっしゃいます。聞いてくる内容が全然違うということは、求めてくるものも当然違う。CVCもベンチャーもそれぞれに目的が違うので、やはりコミュニケーションがいちばん重要ではないかと思います。しっかりコミュニケーションをとらせてもらえると、本体である事業会社と一緒に取り組む事業の未来が読める。事業提携をするときも、スタートから従業員同士が積極的に取り込めるのは、純粋なファンドにはないCVCの良い面だと思います。
スタートアップにとって、単なる資金調達に留まらず、大企業のもつ経験やリソースの提供、その後の事業提携などの展開を期待できるのがCVCから出資を受けるメリットである。しかし、資金以外の何らかの支援を受けることが事業活動への制限になってはいけない。CVCによって目的は個々に異なる。長く付き合える関係を築くには、投資を受けるスタートアップ側も交渉力を付け、十分なコミュニケーションをとってパートナーを選ぶことが大事になってくるだろう。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります