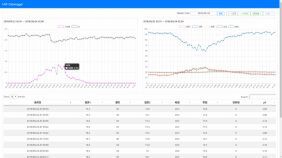日本の農業人口は減少し続けており、2030年には現在の半数になると予想されている。その対策として期待されているのが、ICTやロボットなど最新技術を活用したスマート農業だ。
しかし、農業は気候に大きく左右されるうえ、作物によっては1年に1回しか収穫できず、ビジネスモデルの確立が非常に難しい分野でもある。また、自動化された植物工場が話題になる一方、国内農家の大半を占める小規模農家には、高額なシステムには踏み出せず、導入が進んでいない。
そんな両者の課題を解決するため、スマート農業に興味をもつ新規就農者と、知見を収集したいITエンジニアが連携して、より低コストで現場のニーズにマッチしたIoT機器やサービスを開発する活動が始まっている。今回は、IoTデータ通信サービスを提供するソラコムのユーザーグループから生まれた「農業活用コミュニティ」を取材した。
農業IoT導入に興味があっても手を出しづらい農家の現実
「農業活用コミュニティ」は、ソラコムのユーザーグループから派生した分野別コミュニティだ。メンバーは、機械メーカーやソフトウェア開発企業に勤めるエンジニアが中心。農業地域にある信州や東海エリアのメーカーでは、農業用の自動給水や遠隔制御システムなどの開発案件が増えており、注目の分野となりつつある。2018年3月、ソラコムの通信SIMの農業への活用を模索しているエンジニアが集まり、同ジャンルの課題などの情報共有をするために設立された。
メンバーのひとりの浦野さんは、そのエンジニアコミュニティに参加している果樹農家だ。もともとは医療機械メーカーのハードエンジニアだったが、6年前に実家である長野県での観光農園「雅秋園」を継ぐことになった経歴を持つ。
「実家を継ぐまで農業の勉強をしてこなかったので、さまざまな勉強会に参加して、栽培方法をイチから学びました。しかし近年は異常気象で、ぶどう栽培歴50年の大先輩ですら『こんな天候は初めて』という。従来の知見が通用しなくなっているのです」
天候が読めず、農産物それぞれに合わせた栽培こよみどおりにやってもうまくいかないとなると、ベテランでも音を上げてしまう。もしかしたら、温度や湿度などの環境データを計測して、生物学的に生育を管理すればうまくいくかもしれない。そこで浦野氏は、エンジニアとして培った技術を活かし、温度センサーやかん水装置を自作し、農場に設置した。
新規就農者の相互支援グループ「信州ぷ組」の勉強会で自作の装置を発表したら、思いのほか多くの農家の方が関心をもち、うちでも使ってみたい、と相談を受けるようになったそうだ。新規就農者や若い後継者は、生き残りをかけて、新しい栽培方法や効率化を常に模索している。メディアなどを通じて農業IoT機器に興味をもっているけれど、個別の農家が導入するにはまだハードルが高い。
導入を躊躇する理由は3つある。ひとつは、コストの問題。小さな農家にとって、高額なIoT機器は確実に成果が出るかどうかわからなければ手を出しづらい。浦野さんによると、「個人経営の小規模農家がかけられる経費は、せいぜい年間数千円程度」という。安価なセンサーであっても、毎月のサポートや通信費が千円以上かかるサービスは厳しい。
2つ目は、作物や栽培方法によって、計測したい内容や設置環境が異なるため、市販の製品がすべての現場作業には当然フィットできていない。
3つ目は、圃場に設置するための電気や水道のインフラが整っていない場合がある。工事やサポートまでを業者に依頼すると高額になってしまう。自力で配線や敷設をする手もあるが、ある程度の知識がないと難しく、そこまで手が回らないのが現状だ。
そこで、浦野さんは農業活用コミュニティの仲間と協力して、ボランティアで農業IoT機器を開発し、設置から使い方の指導を含めた活動を行なっている。
地域の栽培データをクラウドで共有し、新しい栽培方法の確立へ
要望が高いのは、温度や湿度などのモニタリングだ。生育に必要な温度や湿度、日数といった条件はある程度わかっているので、理論上では、適切な環境を整えれば一定の収量は見込める。また、新品種の開発や新たな栽培方法を見出すには、正確なデータの蓄積が不可欠だ。
「みんなと同じやり方では、商品価値が生まれません。手探りでやっていた自分たちの栽培方法を科学的に証明するためには、センサーによるデータ収集が役に立ちます。さらに、地域で同品種を栽培する仲間とデータをクラウドで蓄積・共有すれば、より多くのデータから知見を導き出せるかもしれません」と浦野さん。
松本市でトマト農家を営む石綿さんの依頼で開発したモニタリングシステムは、ハウス内2ヵ所の気温、湿度、地温、葉面温度、日射量、土壌水分張力(pF)の6つを計測するBOXと、計測データを管理するウェブアプリからなる。当初は計測するだけでいい、という要望だったが、不在時に遠隔でチェックできるように、ソラコムの通信SIMを使用して計測データをクラウドに転送し、スマホでみられるアプリも開発した。
開発の際は数回にわたって現地を視察し、必要な機能を打ち合わせた。
「親戚に梨農家がいて、近所にも田畑がたくさんあるので、都会の技術者に比べれば農業のことはある程度わかっているつもりでした。しかし、実際に農場を訪問して話を聞くと、まるで想像しなかったことばかり」と沖さん。
浦野さんはハードウェアが専門だったので、ウェブアプリの開発は、ソフトウェアエンジニアの知野さんが担当。さらに、暑さや寒さに強い耐候性のあるケース素材選びは、温室環境モニタリングサービス「あぐりログ」を開発するベンチャー企業・IT工房Zに協力を求めた。
ただ気温や湿度を確認するだけでは商品価値は上がらない。蓄積したデータが成長とどのような相関性があるのかを見出すには、長期間の計測と複数条件による膨大なデータの蓄積が必要だ。できるだけ多くの農家に導入して、データを収集するため、設置後は視察会を開催し、地域の農家の人たちにも見学してもらったそうだ。すでに同様のモニタリングBOXをいくつかの農家に納品済みとのこと。
当初は、スマホでの遠隔モニタリング機能は求めていなかった石綿さんだが、実際に使ってみたところ、小まめにハウス内の温度を確認できるので、外出時の不安が減り、昼間の配達や勉強会への参加がしやすくなった、と喜ばれているそうだ。
農業の勉強会と連携して、情報交換のネットワークづくり
今後、かん水や換気、施肥などの自動化も目指しているが、まずは、ごく簡単な温度や湿度のモニタリングから広げていくという。IoT機器を導入しても、アプリの操作になじまなければ、けっきょく使われなくなってしまうからだ。
「IT技術者だけが集まって製品づくりをすると、どうしても現場のニーズからずれてしまう。農家の方の意見交換をしながら、足並みをそろえて進めていきたいです」と沖さん。
実際に農家で使ってもらうことによって、IoTが農業の効率化に役立つかどうかを知ってもらえる。またIT技術者は、農家が求める機能やサービス、どうすれば導入のハードルを下げられるのかを知ることができる。
12月には、信州と東海地区の農業IoTエンジニアと農家が集まり、農業活用コミュニティとして初のカンファレンスを開催する予定。遠隔地の人も気軽に勉強会に参加できるように、ビデオ会議システムも導入し、草の根から少しずつ活動を広げていきたいそうだ。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります