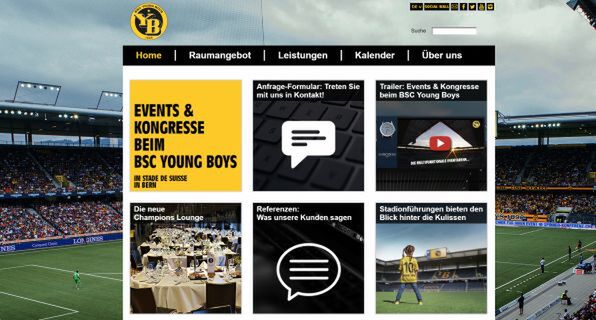日本再興戦略のKPIとして、現状5.5兆円を2025年15兆円へ拡大させようとしている日本のスポーツ産業。そのために企業はスポーツへどう向き合っていけばいいのか。企業のスポーツへの関わり方を早稲田大学スポーツ科学学術院の原田宗彦教授に話を聞いた。
――スポーツビジネスの課題はどこにあるのでしょうか?
日本はスポーツで儲けるという仕組みができていないし、その発想もありませんでした。アリーナビジネスを例にとっても、地方では苦戦しているところがあります。たとえば日本はスタジアムで稼ぐという経験もなく、設計事務所にもノウハウがありません。
チェコフットボールリーグ、スイスリーグなど欧州のサテライトリーグのスタジアムは、収益を生む仕組み、構造を持っています。スイスのヤングボーイズは、複合的なスタジアムになっています。レストランやショッピングモールが中二階にあり、ここからも収益を得ています。日本でこのようなスタジアムが作れるか、儲ける仕組みという点ではまだまだです。
また日本のスポーツビジネスの課題として、企業がお金を出さないという点があります。楽天ぐらい出せば面白くなりそうですが、企業はどこも溜め込みすぎですね。欧州の人からも、”なぜ日本の企業はスポーツにお金を出さないのか、それでは市場が小さいままだ”とよく指摘されます。
――課題解決のためには?
では企業はスポーツに関心がないのかというと、そうではありません。ですが、福利厚生やCSRの一環として捉えているようです。パナソニックのように、スポーツはもっと違う形で使えると理解できると、吹田サッカースタジアム(現パナソニック スタジアム 吹田)への投資のようにスタジアムを建てようなどの動きが出てくる。
それでも、楽天やユニクロのように、数百億円を出して協賛するということはしない。まだ企業の中にスポーツが戦略として取り込まれていないからでしょう。アメリカの大企業にはスポーツマーケティング部があります。ポートフォリオを作って、何にいくら投資するとどれぐらいのリターンになるのかをきちんと計算し、把握しながらやっています。日本企業にはそういう部門すらありません。だからスポーツへの投資が活性化しません。
一方で、東京オリンピックのようなものが来ると、一気に神輿に乗りますね。ワールドワイドオリンピックパートナー、東京2020オリンピックゴールドパートナーなど様々な種類のパートナーを合わせると58社を超えており、4000~5000億円程度集まっているのではないでしょうか。お金は出せるんです。ただ活用できていない、CSR的に社員にボランティアをしてもらうなど、社会貢献で終わってしまうケースが多いですね。
――スポンサー費用を出す以外に、企業のスポーツへの関わり方はあるのでしょうか?
以前Jリーグの社長を集めて、スポンサーシップ、マーケティングなどを教えたことがあります。実業団の人が多数参加しました。そのような取り組みがあったからか、Jリーグにはスポーツビジネスのリテラシーや能力が高い人が増えてきたと感じます。業界全体が良い方向に進んだところで、DAZNの資金が入りました。現在、Jリーグの市場規模は欧州の5大リーグ(スペイン、イングランド、イタリア、ドイツ、フランス)にはまだまだ劣りますが、オランダのリーグには追いつきつつあります。一概には言えませんが、2018年のFIFAワールドカップでの日本の成績(16強)は、実はリーグの実力を示すランキングに符合しているような気がします。

早稲田大学スポーツ科学学術院 原田宗彦教授
――Jリーグはアジア戦略も進めていますね
例えば香川真司選手を育てたセレッソ大阪はヤンマーがスポンサーになっていますが、ヤンマーは耕運機を製造販売しています。フィリピンでは4、5軒の農家で1台の耕運機を借りて使っていますが、セレッソはフィリピンに行って練習をして企業の知名度を上げているようです。
また、日中韓をのぞいたアジアのサッカー大会「AFF Suzuki Cup」(東南アジアサッカー選手権)は、スズキのほかにヤンマーが公式スポンサーとなっています。決勝では5万人以上の観客が集まり、大統領や首相も来る大きなイベントになります。
――サッカーといえば、ヴィッセル神戸がアンドレス・イニエスタ選手をF.C.バルセロナから獲得したことが話題になりました。楽天がイニエスタ選手に払う年棒は30億円とも言われています。
もうそれだけの効果は生まれているかもしれませんね。社員の会社に対するロイヤルティーの向上や、顧客企業へのホスピタリティサービスなどがあります。また、プレミアムチケットを活用して試合の後にイニエスタ選手と握手ができるようにするなどの施策が考えられます。これは正しいサッカーの使い方です。日本にはこれまで本当のVIPホスピタリティーはありませんでした。概念も、接待する場所もなかったのです。
今回、ウィンブルドンのセンターコートに何の前触れもなくロジャー・フェデラー選手がユニクロを着て登場して話題になりました。この宣伝効果は大きいでしょう。広告効果はもう出ていると思います。
――この流れは続くのでしょうか? 全体のパイを大きくするためには、楽天やユニクロに続く企業が出てくる必要があるのでしょうか?
わたしはJリーグの理事を長くやって来ました。今は退任していますが、サッカーが一番可能性があります。一方で、現在の日本サッカー界には”ガラスの天井”のようなものも感じます。DAZNは(ガラスの天井に)ヒビを入れてくれましたが、突き破ってはいません。
選手の価値も低いです。2018年のFIFAワールドカップで負けた日本代表が負けたベルギーは、選手の年棒を合計すると930億円、一方の日本は93億円です。実に10分の1なんです。日本が海外並みに年棒を出すことができれば、海外に出ている選手は戻ってくるでしょう。国内リーグはもっと盛り上がりそうです。また、Jリーグには57チームあるが、それが適正なのか――これについても検証の必要がありそうです。
――オリンピックを始め大型スポーツが予定されていますが、企業が経済的な恩恵を受けるためにはどのようなビジネスマインドを持つべきでしょうか?
DeNA(横浜DeNAベイスターズ)は、アメリカのドジャーズが始めたアクセラレータープログラムを開始しました。DeNAがデータや業界のネットワークなどの資産を提供してスポーツ産業の共創を図るもので、若い人に投資してベンチャーを育てることができます。このようなプログラムは企業がやっても面白いのではないでしょうか。
「ベイスターズ ベンチャー支援でも\横浜優勝/目指す」(関連記事)
http://ascii.jp/elem/000/001/584/1584219/
バンコクでは、体育大学6校から学生を集めてスポーツメーカーを相手にプレゼンをしてもらうというコンテストをやっていました。日本では見られないことです。出てきたアイディアの9割は使えないが、それでいいんですよ。イノベーションとはそういうものですから。
視野にアジアや世界に広げる、伸びているインバウンドをどうするか、高齢化社会をどうするか――このような課題や社会問題に対してソリューションを提供することは、とてもやりがいのあるビジネスだと思います。
原田宗彦教授(早稲田大学スポーツ科学学術院)

1954年大阪生まれ。ペンシルバニア州立大学博士課程修了。鹿屋体育大学助手を経て大阪体育大学教授。フルブライト上級研究員(テキサスA&M大学)を経て現在は早稲田大学スポーツ科学学術院教授。役職として日本スポーツマネジメント学会会長、(一般社団法人)日本スポーツツーリズム推進機構代表理事、(公益社団法人)日本スポーツ健康産業団体連合副会長、日本トライアスロン連合顧問、Jリーグ参与等を務める。著書として「スポーツ産業論第6版」(編著)、「オリンピックマーケティング」(監訳)、「スポーツマーケティング改訂版」(共著)「スポーツ・ヘルスツーリズム」(編著)「スポーツイベントの経済学」(単著)「スポーツ都市戦略」(2016年度不動産協会賞受賞)他多数。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう