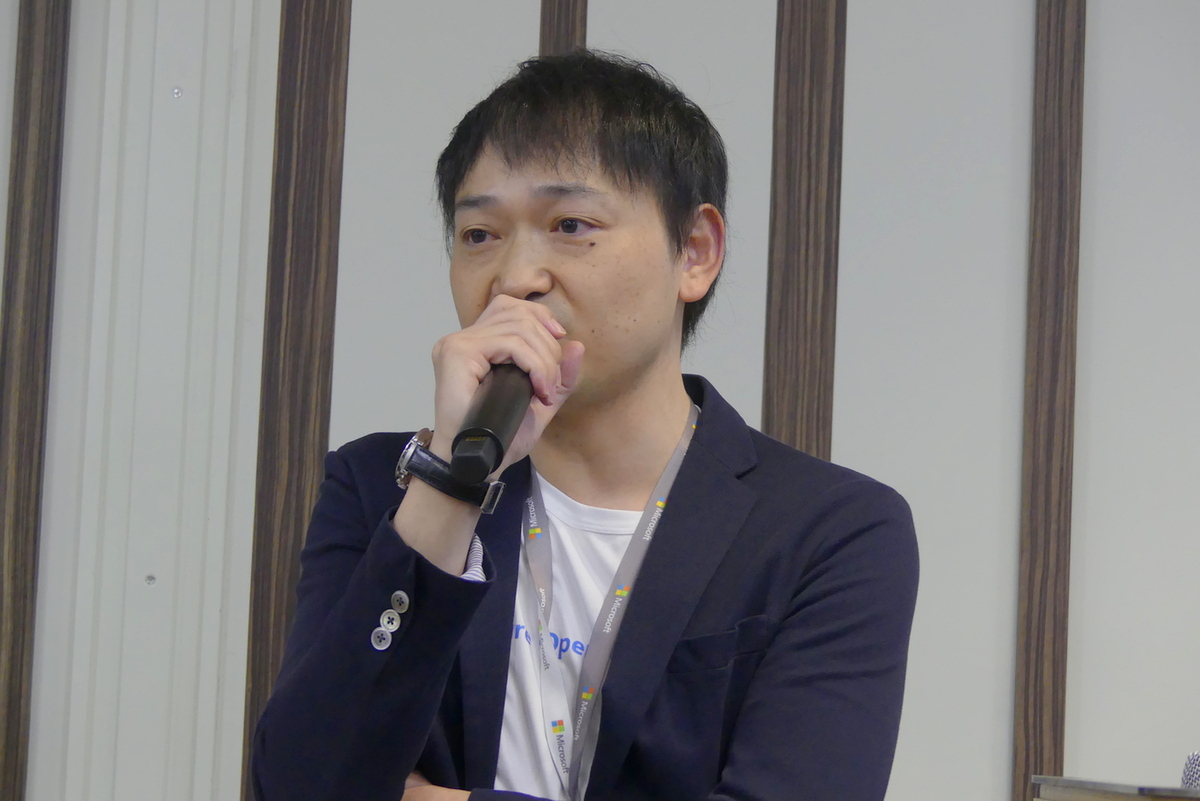2024年は生成AIの利用環境とユースケースが加速度的に進む
生成AIブームの1年間を振り返ったあとは、今後の取組みについて聞いていく。金融庁の牛田氏は「30年前、オープンなネットワークであるインターネットを厳しいコンプラが求められる金融サービスに使おうと考えた人はほとんどいなかったと思う。ただ、インターネットの普及がパンデミック間に合っていなかったら、われわれは金融取引がほとんどできず、社会的に死んでいただろう」とコメント。生成AIへの期待も大きいが、まだまだリスクも捉えられていないため、インターネットがステークホルダーの地道な努力で課題を解決して社会受容を達成したように、今後関係者と多くの議論が必要になると語った。「過度な規制は望ましくなく、自主的なガイドラインの策定など規制以外の手段の含め、リスク低減のため皆様と議論していきたい」とコメントした。
その上で牛田氏は2017年にFSBから公表されたAI/MLに関する報告書を披露。AIの活用が金融安定に資する可能性がある一方で、ガバナンスや説明可能性、監査などの課題も指摘されていたことを明らかにし、公表から7年を経た今でも本報告書で指摘された多くの論点は重要であるとコメント。現状、日本ではAIに特化した金融規制はない一方で、モデル・ガバナンス、個人情報保護、サイバーセキュリティなどに関する規制が適用され得るという。「技術自体を規制することはなく、ユースケースとリスク次第。規制のあり方について、過度なものにならないように慎重に検討していきたい」とコメントした。
生成AIに関しては、今年2月にブラジルで行なわれたG20財務大臣・中央銀行総裁会議声明で、有用性とリスクについて言及された。FSBでは11月のG20会合に向けて報告書を策定予定で、この1年でAIを巡る国際金融規制の議論も進む見通しという。
岡田氏は、「2024年は生成AIのユースケースが出てくる年」と指摘。年末くらいには大手も含めて、AIの利活用事例が明らかになると予言した。一方で、今の生成AI活用は現場ではなく、経営者がギアを握っていることが多いため、ルールや標準規格がない中で、担当者が苦労を背負い込む可能性があるという。「生成AIの勝ちパターンを類型化し、ユースケースドリブンで、法律やリスクを整理しなければならない」と岡田氏は指摘する。
現在、金融データ活用推進協会の生成AIワーキンググループ25社で作っているガイドラインはまさに実務担当者の道しるべになるものだという。「ガイドラインでは金融独自の法規制を考慮した守りを、ハンドブックでは攻めの部分の実務の利活用事例を掲載し、現場の担当者に本当に価値を感じてもらうものを作っていきたい」(岡田氏)とのことで5月にはハンドブックがリリースされる予定だ。「ガイドラインを拡充することでソリューションパートナーへのよろず相談を減らしたい」(岡田氏)とアピールした。
金融データ活用推進協会が作る制度面のガイドラインに対して、日本マイクロソフトは技術面でのガイドラインを整備していく。昨年第11版がリリースされたFISCの安全基準をベースに、4月に技術的なガイドラインをリリースする。「こういうユースケースを実現する場合は、こういうアーキテクチャが望ましいといったパターンを作って、金融機関に提案していきたい」と長町氏は語る。
最後、クロージングとして牛田氏は、「チャレンジしないリスクもあり、生成AIに意欲的に取り組んで頂きたい。技術進展が早く、適切な政策対応を行なうには皆様のような方々との対話が不可欠であり、ぜひ気軽にディスカッションをさせてほしい。イノベーション推進室は金融庁における柔らかいインターフェイスを目指しており、FinTechサポートデスクを通じたよろず相談にも応じる」とアピール。
岡田氏は、「そうは言っても、金融庁が怖いという方は金融データ活用推進協会に気軽にお声がけを」と笑いを交えて応じつつ、「今までは諦めることが多かったが、金融庁や金融機関で双方向のインターフェイスができているので、できないんだったら、むしろルールを作るくらいの気概でいいのではないか」と指摘する。
長町氏は、「2024年はユースケースが拡がる年だと思うが、せっかく生成AIのサービスを展開しても、ユーザーが使ってくれないと、真の業務改善にはつながらない。ユーザーへの利用の定着化という観点でもみなさんと議論を深めたい」と説明。ユーザー目線のアプリの組み方や仕掛けが必要になると聴衆にアピール。モデレーターの巴山氏も、「生成AIはやらない選択肢はない。これからパートナー様の力を借りて、金融機関をより発展させていきたい」とまとめた。
パートナー4社がAIの取り組みを披露
ミートアップの後半は、パートナー4社が金融業界向け生成AIの取り組みを披露した。
トップバッターはSCSK ソリューション事業グループ クラウドサービス事業本部 副部長の石井貞好氏だ。SCSKはいわゆるSIerとして、システム構築から運用、コンサルティング、BPOまで幅広く顧客のニーズに応えており、8000社の顧客のうち2割以上が金融業界だという。
今回、発表されたのはコンタクトセンターに必要な機能をプライベートクラウドで提供する「PrimeTiaas」の自動要約オプション。顧客の声をテキスト化した上で、生成AIを使って認識・要約することで、オペレーターの応答記録の品質向上や対応改善にも役立てるという。もちろん、プロンプトを組むことで、顧客の声やFAQの候補を自動抽出することも可能だ。
続いて登壇したJTP ソリューション事業本部 為田光昭氏は金融機関にも特化した機能を備えるAIインテグレーションを紹介した。JTPは幅広くクラウドの設計、構築、運用、監視などを手がけてきたが、最近は「Third AI」というブランドでAIのインテグレーションサービスを提供。「Azure OpenAI Serviceリファレンスアーキテクチャ Advancedパートナー」として高セキュリティのChatGPT環境を提供しており、Web以外にもMicrosoft Teams、Slack、LINEなど幅広いインターフェイスで利用できるという。
為田氏は金融機関の要望トップ3を披露。3位はオプトアウト申請、2位はCCC(Customer Copyright Commitment)への対応、そして1位はSaaS製品の専有化だという。
3番手として登壇したPKSHA Workplace FieldSales部 村岡利彰氏はAIを活用した社内ヘルプデスクを提案する。同社はAIアルゴリズムの研究・開発を手がけるPKSHA Technologyの子会社で、AI SaaSを手がける。金融業界での実績がとりわけ高く、採用する銀行は47行、アクセスは480万/月に達するという。
同社の独自アルゴリズムとChatGPTを組み合わせた「PKSHA AI ヘルプデスク」はFAQ、社内文書検索、有人チャットをオールインワンで提供する。問い合わせ内容をFAQ化するのも容易で、ナレッジマネジメントとしての利用も可能。某金融機関ではFAQの生成や社内文書検索に生成AIを用い、有人チャットの割合を3割まで下げているという。
最後に登壇したフェアユース代表取締役の足立洋介氏は、金融機関の監査要件を満たすTeamsの録画ソリューションについて紹介した。本製品はTeams会議の通話を自動かつ強制的に録画・録音できる。これにより、監査要件を満たさないためそもそもWeb会議ができない、画面共有ができないといった金融業界特有の課題を解消するという。
すでに大手証券会社のうち一社でカスタマイズ開発を行ない全従業員分のライセンスを提供済み。Azure AIを用いた会議内容のテキスト化や翻訳、インデックス化による検索対応、GPT-4による要約も可能だという。
AIパートナーのためのイベントも続々
最後は日本マイクロソフトの施策やイベントの告知が行なわれた。AIパートナーのためのコミュニケーションプラットフォーム「AI Business Group」が紹介されたほか、事例やソリューションの登録も募集中。3月18日時点での登録事例数トップはFIXER、金融業界の事例は野村総合研究所がトップとなっている。
また、パートナー企業で活躍するエンジニアを表彰する「Microsoft Top Partner Engineer Award 2024」もエントリが開始され、本年度はAIのカテゴリが新設されたという。応募期限は4月29日(月)17時まで。さらに5月29日にはグランドハイアット東京でAIやCopilotを用いたユースケースの構築について学ぶライブスキリングイベント「Microsoft AI Partner Training Roadshow Tokyo, Japan」が開催される。
イベントは最後にネットワーキングとなり、登壇者や参加者が交流を深めた。Columbus Dayは来月以降も開催される予定となっている。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう